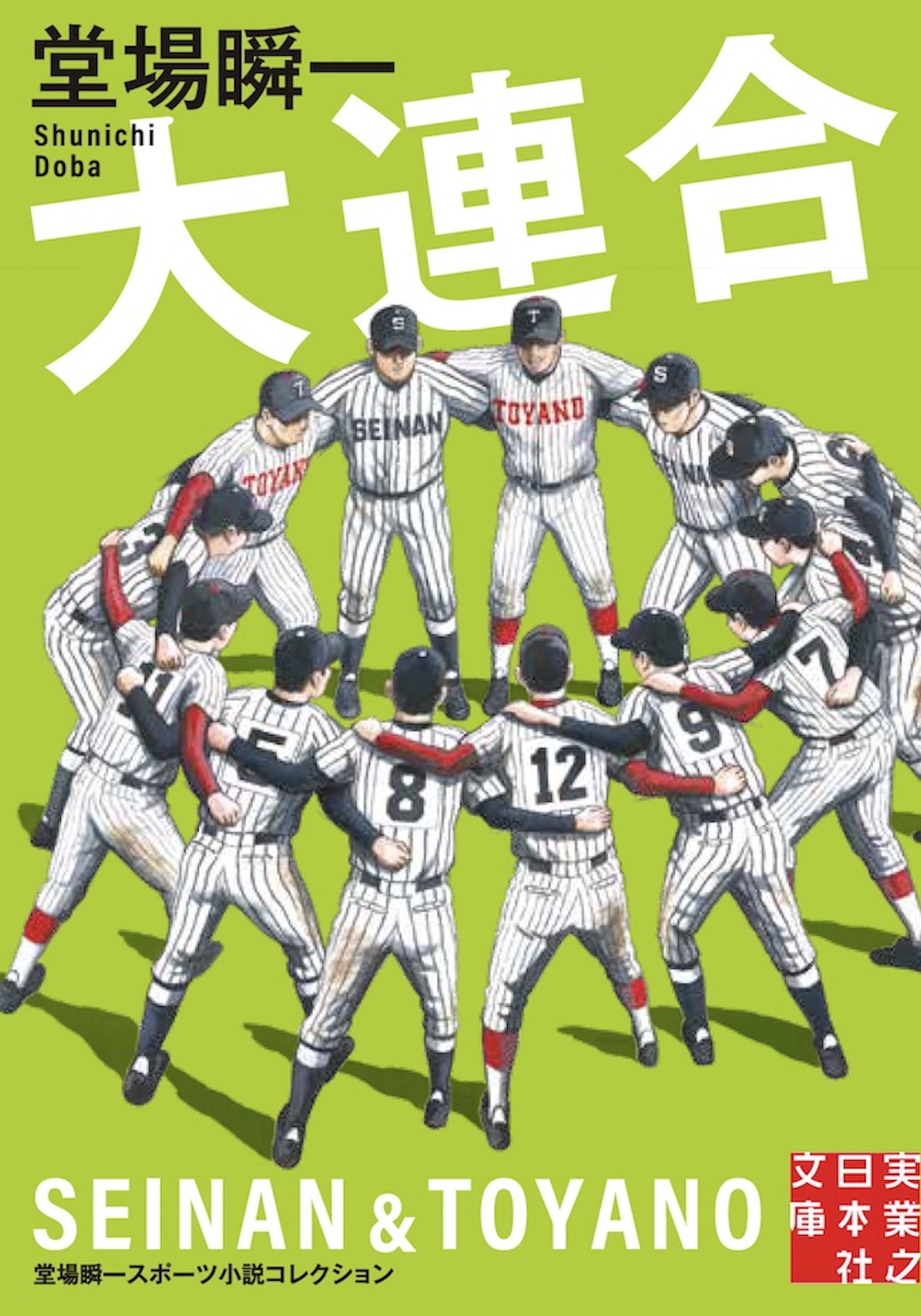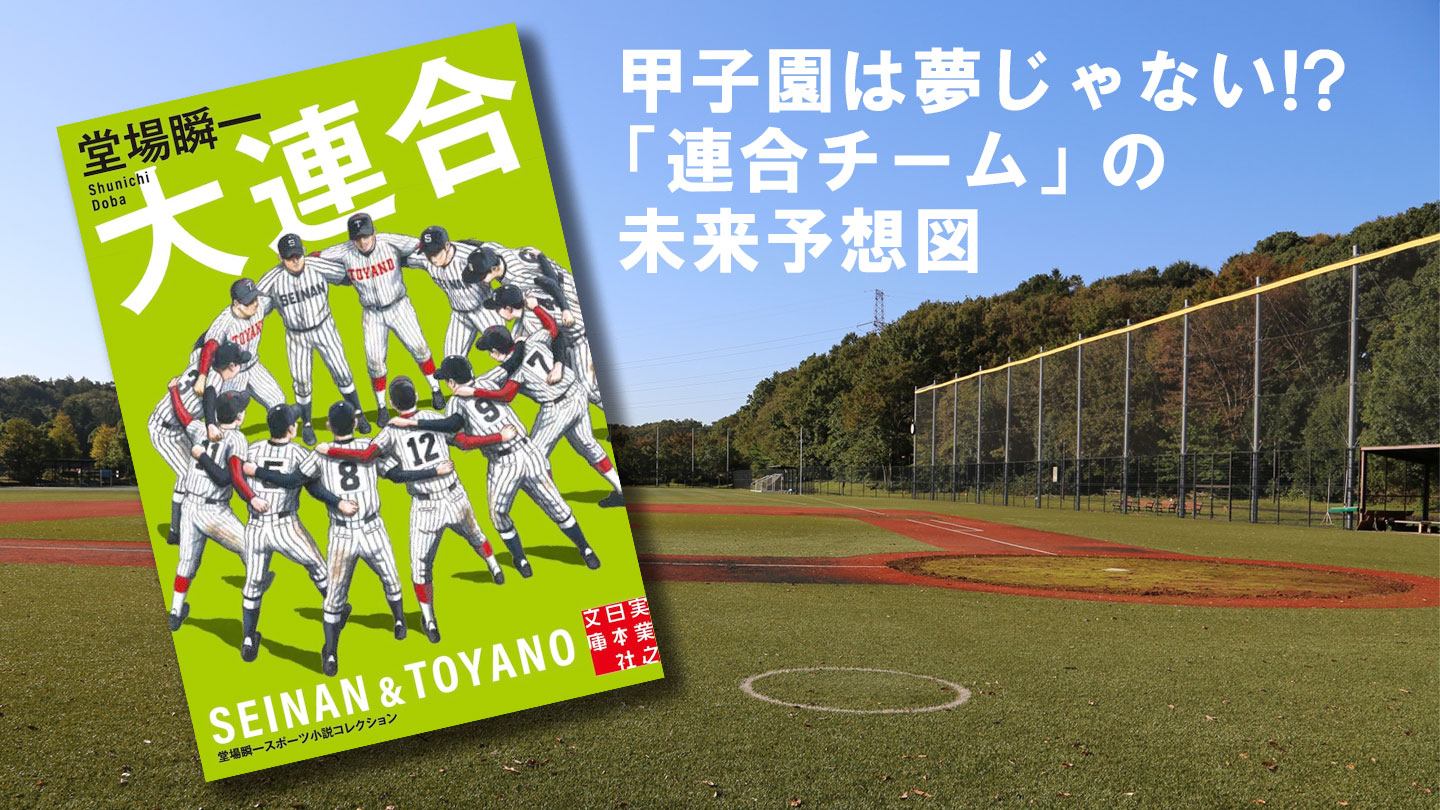
堂場瞬一『大連合』作品解説甲子園は夢じゃない!? 「連合チーム」の未来予想図 沢井 史(野球ライター)
作品紹介
2025.07.01
少子化や競技人口の減少により、公立高校の野球部で部員不足が深刻な課題となっている中、複数校で構成する“連合チーム”が、新たな高校野球の形として注目を集めている。総参加チーム数は徐々に減る反面、連合チーム数は増加。日本高野連によると、2025年夏の全国高校野球選手権大会に、全3396チーム中、155(439校)の連合チームが参加するという。
高校野球界を熟知するスポーツライターが、堂場瞬一氏の小説『大連合』で描かれた連合チームを組む球児の姿を通して、野球をめぐる時代の変化と、大人たちが果たすべき役割は何かを探る。
夏の地方大会を数カ月後に控えた日に、突然の悲劇に襲われた新潟成南高校野球部。指導者の行き過ぎた指導により部活動が制限され、苦悩を抱える鳥屋野高校野球部。その二校が連合チームを組むことになった新潟の高校球児たちのストーリーは、両校の葛藤や障害が立ちはだかる中で、様々な本音を抱えた球児たちがぶつかり合いながらも、やがてひとつになっていく彼らの姿が、手に取るように伝わってきた。
両校の選手たちの共通の思いは「甲子園に行きたい」、ただそれだけだ。それが実現できなくなった現実に直面し、最悪の状況も覚悟したが、鳥屋野高の尾沢朋樹の「成南と鳥屋野で連合チームを組む」という発想から事が少しずつ動き出していく。
当初は周囲からの否定的な目の方が多かった。だが、尾沢が素晴らしかったのは、その信念を曲げなかったことだ。周囲の大人……学校の校長先生までも巻き込んで、様々な情報を得ながら、成南サイドの思いを汲みつつ、少しずつ距離を縮めていく。成南のエースの里田史也は、自身の身体や心の傷もあり連合チームに対しては後ろ向きな印象を抱いていたものの、尾沢との交流を深めるうちに、自然と合同練習に足を向けるようになった。もちろん、互いの実力も認めていたうえで成り立った部分もあるだろうが、共に同じ方向を向けるようになったのは心と心が通い合えるようになった証だろう。
新潟県は南北に県土が広く、互いの意向が合ったとしても連合チームを組むことは困難な場合もある。だが、徒歩10分ほどの距離にある両校がひとつのチームとなって戦うことになったのは、どこか運命めいたものもあった気がしてならない。
ただ、もし自分が指導するチームがよもやの事故に遭い、夏の大会の出場に暗雲がたちこめることになったら……。周囲にいる大人として、どうしていただろうかとふと考えた。選手たちが負ったケガの状況にもよるかもしれないが、いくら入院する選手が多くても、練習再開が未定であっても、人生で一度きりの高校3年生の夏を、簡単に〝夏の大会までにチームが戦える見込みが立たないから、出場は諦めましょう〟など彼らに言えるだろうか。この夏の大会のためにずっと努力してきた彼らの姿を見てきたのに、最も残酷な宣告をしなければならない立場だったとしたら……。最善策を模索しながらも、やはり私も共に手を取って前を向いていけるチームを探し当て、頭を下げに行っていたかもしれない。
数年前は「連合チーム」と聞いても、どこか遠い存在にあるような感覚を覚えたが、最近はとても身近に感じるようになってきた。少子化、競技人口減少……。最近の高校野球を取材していくと、必ず話題になり今では最も大きなテーマとなっている。子供の数が年々減っていることは近年では覚悟をしていたとはいえ、予想以上の減少度の速さに戸惑いが隠せない現場も多いはずだ。
かつて日本高校野球連盟への加盟校数は年を追うごとに増加傾向にあり、平成17年(2005年)には4253校とピークを迎えたものの、以降は年々減少の一途をたどっている。平成29年(2017年)には3989校と4000校を割り、昨年(令和5年)は3818校となった。さらに少年野球の現場はもっと深刻な状況にあると耳にする。少年野球が盛んだった地域でもチームの統廃合が続き、少年野球が専用として使っていたグラウンドが、今ではサッカーチームの練習場になっているところもあった。
子供の数が減少しているだけでなく、最近ではボールを使った運動を制限するグラウンドが増えていることもあり、練習場所の確保の難しさに頭を悩ませる指導者も多いという。人口が多い地域=野球チームが多いという先入観もあるが、現代ならではの問題にぶち当たり、活動を制限せざるを得ないチームもある。
こうして少年野球チームが減少すれば、高校で野球をする子供も当然少なくなる。技術に長けた子供は私学強豪校からの誘いがあって様々な選択肢が増えるが、そうでない子供は高校でも野球を続けるか、大学進学を見据えて勉強に打ち込むかの二択を迫られる。野球はやりたいけれど、甲子園に行けるのかも分からないし――。自分の実力に限界を感じてしまう子供も多いだろう。だが、そんな子供たちに手を差し伸べる取り組みを大阪東部のある府立高校が主導して行っている。近隣地区の高校と協力して、中学生の野球少年を対象に晩秋の時期に野球教室を開催しているのだ。高校野球への関心を高めてもらうのが狙いだ。近隣の高校から数名ずつ選手が出向き、数人の中学生とグループとなり硬球での指導に当たる。そこで、高校野球の楽しさや夏の大会に向けたやりがいなども話し、彼らの意欲を高める。その府立高校は進学校ということで元々中学生球児からの関心は高かったとはいえ、現在は1学年で20人前後の部員が在籍しており、大学でも野球を続ける選手がほとんどだという。
ただ、一般的には公立高校は部員集めに苦労しているケースはよく耳にする。本気で甲子園に行きたいなら、声が掛からなかったとしても練習設備の整った私学を志す子供が多いからだ。それでも何とか自宅から通学できる範囲内の公立高校で野球を続けようとする子供もいるが、その数は年々減っており近年は新入生が1ケタに留まってしまうことは珍しくないと、大阪の北摂地域の監督が明かしていたことを思い出す。
3年生が引退したばかりの秋の新チームでは、1、2年生の2学年のみで戦うことになるが、いずれの学年も1ケタの部員しかおらず、9人に満たない場合も多い。「ケガ人や熱中症で倒れてしまったら試合ができなくなるので、そこは指導者として細心の注意を払いながら練習もしていかなくてはならない」と話す監督もいた。部員が少なくなればなるほど単独で野球部として活動することが難しくなり、3校、4校……多くは5校以上で連合チームを組むケースは、秋季大会で特に多く目にする。
連合チームという言葉にはネガティブなイメージを抱く者もいる。だが、本文中には「日本代表も色んなチームから選手が集まってひとつのチームになるじゃないか」というセリフもある。確かにそうだ。連合チームはどうしても〝寄せ集め〟という印象を持たれがちだが、多くの特色を持った選手たちが集ったチームでもある。ただ、高校野球の場合は、同じ学び舎で机を並べ苦楽を共にしてきた仲間たちとの集大成として捉えられがちで、特に夏の大会は他校同士でチームを組むことに抵抗を感じる者もいるだろう。
2024年になったばかりの冬の日に、和歌山県のとある公立高校を取材した時、監督がこんな話をしていた。
「子供の数が減ってきていることは、数年前から我々も危惧してきたこと。それでも目の前にある状況を受け止めてやっていかなければいけない。子供が減っていても、彼らの思いに見合った指導ができるよう、指導者もアップデートしていかなければならない」
高校野球界では、厳しい言動での指導や場合によっては体罰も横行していた時代があった。昭和真っ只中の頃がまさにそうだ。今でもそういった指導が取り沙汰され処分を受ける指導者もいるが、近年はそういった行き過ぎた指導に厳しい目を向けられる傾向が高く、指導のあり方が問われるようになった。
ミスをしても頭ごなしに怒るのではなく、なぜミスをしてしまったのか。そのミスをどうすればなくせるか。選手に考えさせ、頭にインプットさせる。声色や勢いで選手に圧をかけて叱るスタイルはもう古い。選手たちの意欲を搔き立てつつ、自立を求める指導が現代においてスタンダードとされている。怒鳴る指導から説く指導へ。これは野球に限らず、スポーツの指導の現場において変わろうとする指導者をよく見かけるようになった。
かつては野球といえば猛練習が代名詞だった。とにかく時間をかけ走る、バットを振る、ノックを受ける。数をこなしてなんぼという〝根性野球〟が定番だったが、今は量より質を重視する練習方法を採用する学校も増えてきた。長くダラダラと練習するのではなく、中身を追求する手法で、敬遠されがちだった悪いイメージを払拭し、子供たちに少しでも野球への興味を高めてもらいたい。トップチームを筆頭に様々なカテゴリーの選手たちが、子供たちが野球に触れる機会を作る取り組みが近年は徐々に盛んになっている。
野球界にこびりついていた悪しき慣習を除去しながら、時代に沿った指導法、そして野球の楽しさ、素晴らしさを野球に長年携わってきた大人たちが伝えていくべきなのではないか。子供の数が減っている現実も受け止めつつ、少ない〝幼い目〟に野球への興味が湧いてくれることを願うばかりだ。
さらに、新潟成南と鳥屋野のように、連合チームとして夏の地方大会を勝ち上がり都道府県の代表となる日は現実的にそう遠くはないだろう。そのためにも柔軟な対応ができるよう、都道府県の高野連をはじめとする各機関が体制を整える必要がある。部員が少ないからと言って一緒に練習するのは難しいから……と出場に難色を示すことは絶対にあってはならない。誰一人もが、思うように白球が握れる環境を確立できるよう、その時、その時代の状況にアンテナを張りながら、私たち大人も野球少年、少女の夢を手助けしてあげたい。
*本記事は、文庫『大連合』巻末解説を再録したものです。