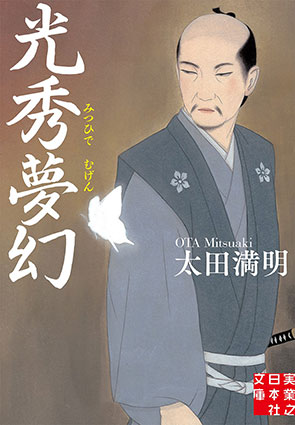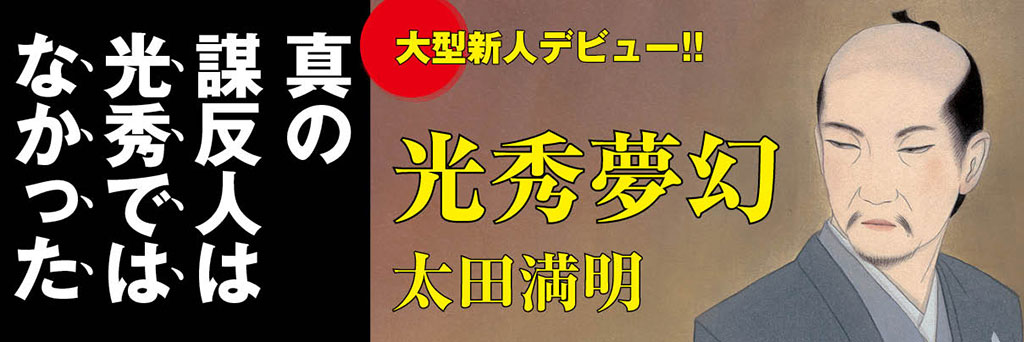
12月の文庫新刊 太田満明『光秀夢幻』作品解説
明智光秀の大戦を描く驚嘆のデビュー長編 縄田一男(文芸評論家)
批評家にとって最も嬉しいことの一つに、やがて、斯界を牽引してくれるであろう新人との出会いがある。
私の場合、太田満明の本書『光秀夢幻』が正にそうであった。明智光秀を主人公とした作品としては、光秀の号を題名とした中山義秀『咲庵(しょうあん)』に次ぐものといっていいのではあるまいか。
『咲庵』は光秀ものの最高峰であり、その意味でいえば本書はナンバー2、すなわち、新人の処女作にしては完璧ということになる。気のはやい読者は、二〇二〇年度のNHK大河ドラマの主人公が明智光秀だから、この一巻もある種の便乗作品と勘違いするかもしれない。だが、そうではない。作者は過去にこの作品の原型ともいうべき長編を二度、第十五回歴史群像大賞に投じ奨励賞を受賞、さらに、第七回日経小説大賞に投じ、こちらは最終候補に残っている。そして今回の正に執念の、というべき刊行。モノが違うのである。
さて、この一巻は、織田信長が、明智光秀らを安土城天主の最上階にまで随伴するところからはじまる。その折、信長は、ふと、
「やはり、わしが公方(征夷大将軍)の位を取って代わるべきであるかな」
と口にするところからはじまる。
日本には言霊という考え方がある。言葉に内在する霊力のことで、往時、言語が発せられるとその内容が実現されると信じられていた。この一巻は、信長の言霊によって多くの人々の運命が翻弄されてゆく物語といえよう。
そしてこの時、天井に描かれた天人影向や三皇五帝、孔門十哲らの絵画が「眼下の人間どもを憐れむかのように冷笑、いや憫笑を浮かべていた」という。すばらしい書き出しではないか。
私はまず、この静謐な文章に魅せられた、といっていい。そして、作者はこの一巻の中の様々な箇所――人間の欲望がむき出しになる戦場の場面や、武将たちが水面下で次々と放つ諜略戦などで、明らかに文体を変えている。いや、そういう言い方が適切でないなら、文体の温度を変えている。
と、ここまで書いてきて、私は、この優れた作品を、作品をして語らしめる他に手が浮かばない。従って、この解説は、本書を読了された方のみにその効用があると思っていただきたい。
そして信長の「どうだ、(公方に)なれるか」という言葉に呪縛された光秀は、このときから「世を一変させる大きな謀事」に奔走することになる。また信長のために一命を捧げている光秀を一方で「佞臣」といっているのも面白いではないか。が、これも一つの伏線でもあるのだが――。
やがて光秀の中で一つの欲望がメラメラと音を立てて燃えはじめる。それは弥平次秀満が「(殿は、人変わりなされた……。近頃はまるで胸の中で、火薬庫の火力にまさる情炎が燃え盛っているかのようだ)」と案ずるほど。
そして、信長が公儀になるという「夢幻」が、忽然と姿をあらわしたとき、同時に浮かび上って来るのは、朝廷と綿密なパイプを持った光秀に他ならない。が、これまで征夷大将軍になったのは源氏のみ。そこで光秀は古記録を調べに調べ、平氏の出である信長が将軍になり得る根拠を見出す。私はこんな書かれ方をされた光秀を他に知らない。
やがて光秀の野心はどんどん大きくなり、
(その天下の草創、この明智光秀をおいて他のたれが為しえるか)
と、機構による政治=公儀を夢想するようになっていく。
が、ここにも光秀の構想を面白がらぬ者がいる。羽柴秀吉である。主君が将軍になることを喜ばぬ者はいない。ただ、そうなれば、権力の中枢に坐るのは光秀ではないか。しかも彼奴は、かつては足利義昭の家臣であったにもかかわらず ――。
が、その光秀に危機が訪れる。「気難しい信長が織田家を公儀とすることに魅力を感じなければ」彼はただの〝宙ぶらりんの男〟となってしまう。
そして、織田家家中に拡がる光秀への嫉妬。旧主を弊履の如く捨てた、新たな主君信長への追従の巧みさ、異常なまでの出世のはやさ、禁裏を相手とした役職の重大さ等々。
さらに、ここに登場するのが乱世の怪物・安国寺恵瓊。作者は記す。このことによって、明智と毛利と羽柴の奇術まがいの掛け合いは、このようにして幕が上がった。
そして、これが本能寺の変の遠因となる作品を私は知らない。紛れもない、これは作者の手柄であろう。
明智が信長を将軍位につけるのがはやいか。それとも秀吉が高松城を落とすのがはやいか――こんなドラマが隠された本能寺の物語を読んだことがおありだろうか?
そして黒田官兵衛はいう。
「しかし、かくまでおのれの策が破れてしまった上は、明智殿に残されているのは窮余の一策だけではありますまいか」(傍点引用者)
と。
これを聞いた秀吉の「(明智を追いつめるために)自分のしでかした事に戸惑うような表情になっていた」という描写はどうであろうか。
最大の敵こそが最もよく自分のことを知っている――光秀がこのときの秀吉の表情を知ったら何といっただろうか。
が、戦国は無残なものである。
秀吉が信長の死を予測しつつ
「我が方としては、いかに手を打つか」
と官兵衛に尋ねると
「……明智と毛利の連絡を根こそぎ絶つことです」
と即答する。
すべては、あの日、光秀が信長らとともに安土城の天主の最上階に登ったときからはじまった。男たちは、それぞれに「夢幻」を追い、誰一人として、天井画に秘された、憫笑を理解する者はいなかった。
そして信長の発した言葉――。
何と力強い新人の登場であろうか。
が、太田満明は、昨日や今日、作家になったのではない。
最後にその略歴を紹介しておくと、作者は一九六〇年、兵庫県三原郡(現・南あわじ市生まれ)。大阪教育大学卒。兵庫教育大学大学院修士課程修了。修士論文は「司馬遼太郎作品論」。
歴史読物に『桶狭間の真実』『桶狭間伝説の嘘』。
前述の如く、第十五回歴史群像大賞(『歴史群像』二〇〇九年六月号)奨励賞を受賞。但し、題名は本書のネタバレとなるので敢えて記さない。さらに二〇一五年、第七回日経小説大賞で『織田幕府幻想』で最終候補作に残る。また、一九九八年「敗残兵の英雄史観 ――司馬遼太郎論」が新潮新人賞の予選を通過。
こうして見ていくと幾星霜の雌伏期を経てようやくデビューを飾った作者こそ、真の強者(つわもの)ではあるまいか。
次作が待たれる所以である。