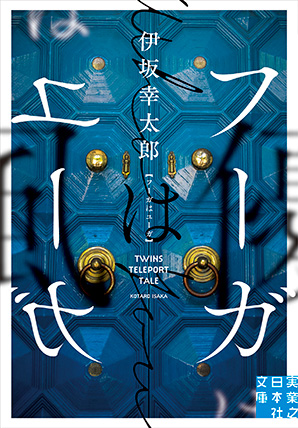2021年10月文庫新刊 伊坂幸太郎『フーガはユーガ』作品解説
現実はそんなに甘くない。でも、生きていこうよ。 瀧井朝世(ライター)
現実はそんなに甘くない。
でも、生きていこうよ。
伊坂幸太郎の作品を読むと、いつもそう言われている気がする。軽快な語り口調で進行する物語の主人公たちが置かれた状況は、決して甘くはないことが多い。それでも、この先の人生にちょっとだけでもいいことがあるといいよね、だから生きていこうね――そんなつぶやきが聞こえてくるように思える。
本作『フーガはユーガ』で描かれる家庭環境も、いくらでもシリアスに書けるほど苛酷だ。それを、どこかとぼけた一人称の語りと、ファンタスティックな要素と、構成の妙でもってエンターテインメントに仕立て上げてのけている。では、最後のページで見せてくれるのは、どんな光景なのか。
仙台のファミリーレストランで向かい合う二人の若い男。一人は常盤優我という青年、もう一人はテレビディレクターの高杉で、二人はこれが初対面だ。優我が高杉に語り始めるのは、双子の弟である風我と、彼らが持つ不思議な能力の物語。暴力を振るう父親と、何もしてくれなかった上にやがて出奔する母親のもとで育った彼らが小学生時代に気づいたのは、自分たちに備わった、毎年誕生日の一日だけ、十時十分から二時間ごとに身体が入れ替わる奇妙なテレポーテーション能力だ。検証を重ねて力の特性を把握した彼らは、いじめられっ子のワタボコリを助けたりもする。でも、道ですれ違った家出少女を救えなかった出来事が、主人公たちのなかに深い悔恨となって刻まれる。
二〇一八年の単行本刊行時にご本人にインタビューしたところ、予想外の話が飛び出し面白かったのでご紹介しながら話を進めたい。ただ、伊坂さんはいつも朗らかで飄々としていて取材中も終始笑わせてくれ、そのぶん、どこまで本気でどこまで冗談で言っているのか分からないところがある。と、心にお留め置きいただきたい。
まず、実業之日本社からの小説の刊行が二〇〇五年発表の『砂漠』以来であるが、その経緯と本作の着想について訊くと、
「『砂漠』を出した時、担当編集の方に双子が生まれたんですよ。それで〝次は双子の話を書きましょう〟という話になって」
と、なんともユニークな出発点を教えてくれたが、他にも兄弟が登場する著作はあるため、さほど突飛な発案ではなかったはずだ。その後、他社の本の仕事に追われるなどして時間が空き、そろそろ取り掛かろうとして思いついたのが、「誕生日だけ二時間おきに互いと意識が入れ替わる双子の話」だった。だが、ほどなく一作の映画が公開された。あの大ヒット作品である。
「『君の名は。』が公開されて、これは絶対にヤバイ、真似したと思われる、と(笑)。あの映画自体好きですし、悩んだ末、苦肉の策で意識だけでなく身体ごと入れ替わるという設定にしました」
テレポーテーションのルールを設定していく作業は楽しかったそうだ。毎年誕生日だけ、二時間おきの現象だという他、手に触れているものも一緒にテレポートする、乗り物の中にいてもそれごと移動するといったことはない――等々。
「フィクション作品では、大きな噓は一個だけならアリかなと思っていて。それを成立させるために細かな制約を設定していくのが僕の作風でもある。ここで瞬間移動だけでなく透明人間にもなれる、なんて噓を重ねると著者に都合がいいだけの設定になるので、噓はひとつだけ、ですね」
細かなルールがあるほど主人公たちの行動にも制限が生じるが、それにしてもこの力、なんとも活用しづらそう。超能力者だといっても、彼らはまったくもって万能ではない。その設定については、『逆ソクラテス』刊行時のインタビューでの著者の発言を引きたい。
「お話だと結局、最後にこの子が何かの能力で成功しました、とかいう話になりがちですが、でも実際はそういう能力がない人が大半じゃないですか。だから、そうじゃない話も書こうという話を編集者としました」
まったく異なる内容についてのコメントではあるが、これは本作にも当てはまるのではないか。風我たちが持つのは現状を軽々と変えられる圧倒的な力ではなく、使えるのかどうか分からないへんてこりんな能力。だからこそ、彼らに親しみが持てるし、力をどう活用していくのかという興味をわかせる。
また、主人公が第三者に自分の過去を語っている構図も本作の大きな特徴だ。高杉が時折「それはどういうことだ」とツッコミを入れるが、読者も同じ気持ちだ。さらにこちらを用心させるのは、優我が何度も、自分の話には噓が混じっている、と念押しする点。自ら名乗り出る「信用できない語り手」なのである。それに関しては、
「後からこいつは信頼できない語り手だったと分かるより、最初から堂々と〝噓も入ってるよ!〟と言っておいたほうが読者に対して親切な気がして」
と笑っていたが、この構造こそに、ストーリーテリングの巧みさがある。もしこれが幼い頃から時系列にそって進む話なら、読者は双子が能力を活用して困難を乗り越える展開だと予想するはず。それでは大きな牽引力は生まれない。主人公が過去を語るという枠組みだからこそ謎は生まれてくる。なぜ彼は初対面の男に自分たちの秘密を語っているのか? 現在、優我と風我はどんな生活を送っているのか? 自分の話に噓の部分があると何度も繰り返す狙いは何なのか? そして読み進めるうち、読者は願望を持つはずだ。双子の家族環境、他の子どもたちが晒される非情な運命が全部、優我の噓だったらいいのに、と。大逆転がありますように、と。
そう、この物語では多くの子どもたちがひどい目に遭う。命を落としてしまう子もいる。ユーモアを交えて語りながらも、そこに広がる世界はかなり辛いのだ。双子の置かれた環境については、こう語ってくれた。
「僕は家族がチームとなって敵に立ち向かう話が好きなんですが、世の中そんな家族ばかりじゃない。過酷な状況を生き抜く子たちだからこそ、突飛な能力があっていいんじゃないかと思い、辛い家族環境の主人公にしました。そのほうが二人で乗り越えていく感じが強まりますし。ただ、この能力でできることって、そんなになくて、かなり地味(笑)。そこがいいなと思っています」
他の子どもたちに関しても配慮がなされている部分はある。たとえば、小玉という少女が受けている虐待について、直接的な性的虐待ではリアルすぎるからと、それは回避したそうだ。また、今回の文庫化に際して彼女が電気ショックを受ける場面が削除されるなど、ややマイルドになっているのも考慮の末だろう。
ただ、それでも、子どもたちに起きる出来事はあまりにもひどい。なぜこうしたことを書くのか。それはやはり、この現実世界で、実際に子どもに対するひどい行いが多々存在しているからではないか。過酷な状況を乗り越えられずにいる子どもたちは現実に沢山いる。その事実から、目を背けられない著者の姿勢を感じてしまう。伊坂さんはよく「作品にメッセージはこめないけれど、自分の考えが出てきてしまう」と話しているから。
双子たちも、降りかかる暴力に抗いきれずにいる。それでも智恵を絞って邪悪な存在に立ち向かっていこうとした時、彼ら、特に風我の原動力となっているのは純粋な正義感ではなく、怒りだ。彼らは正義のヒーローとして世の中を助ける善人ではない。特別な大義名分だってない。彼らはただ、暴力を受けた、あるいは暴力を目の当たりにした生身の人間として、怒っているのだ。無力な子ども、かつて無力な子どもだった大人の消えない怒りが、ここにはしっかり書かれている。見過ごされがちな誰かの心の傷とそこから生まれる感情が、書き留められているのだ。怒りに駆られた暴力という反撃を、分かりやすい勧善懲悪な物語や美談に落とし込んだりしないという、冷静さを保ちながら。
それにしても、エピローグともいえる終章の語り手には驚かされる。本篇未読の方のために詳しくは書けないが(なので勘のよい方はここから先の六行は読まないでください!)、彼が語り続けていると思わせてくれるところに、小さな希望が感じられる。ツッコミをいれながらも見守ってくれているんだというところに、絞り出すような慰めが伝わってくる。それは、コインロッカーに入れたラジカセで歌を流し続けるのと同じタイプの祈りではないか。そういえばご本人も、この切なさや独特な余韻について、「『アヒルと鴨のコインロッカー』と似ているかもしれません。そういう意味では、原点回帰的な小説になりました」と、語っていた。
すでにいくつかのインタビューやエッセイでも言及されているが、著者には小学生時代、恩師の磯崎先生から教わった忘れられない言葉があるという。それまでは「優しい」という言葉に対して「人に親切にする」というイメージを持っていたが、
「磯崎先生が言うには、にんべんに「憂」と書くから、人の嫌な気持ちを分かってあげるのが本当の優しさなんだ、って。別に親切なことをしなくても、人の嫌なこと、つらいことを分かってあげるのが優しさだというのがちょっとしたカルチャーショックだったので、初期の『ラッシュライフ』でパクって泥棒に言わせているんです」
楽しいフィクションを書きたい。だけれども、現実に辛い状況下で憂える人を置き去りにしてしまうような絵空事は書きたくない。そんな(無意識下の)思いが融合した結果、ほろ苦い作風が生まれているのではないだろうか。つまりこの小説は、著者の優しさの表れなのだ。