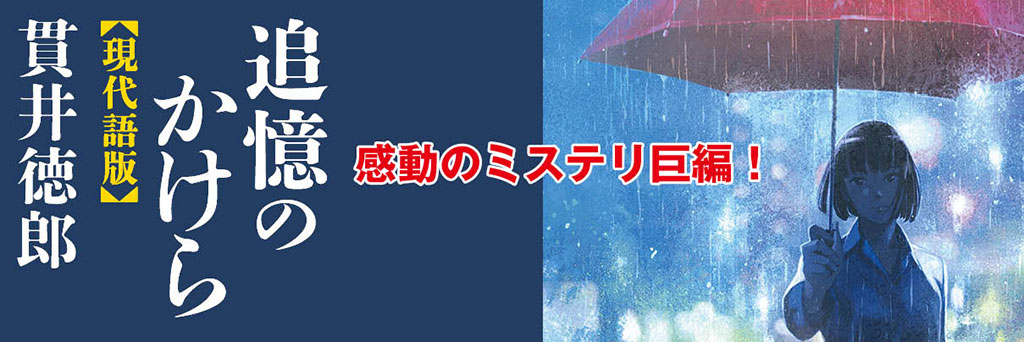
2022年8月文庫新刊 貫井徳郎『追憶のかけら 現代語版』作品解説
善意のバトンと今、この小説を読む意味 野地嘉文(ミステリ研究家)
貫井徳郎の作家デビュー三十年と実業之日本社の創業百二十五周年を記念して、貫井徳郎文庫作品連続刊行プロジェクトが始まった。六月に出た『プリズム』に続く『追憶のかけら 現代語版』はその第二弾にあたる。作品に包含されている登場人物による手記はこれまでは旧字旧仮名づかいになっていたが、今回の刊行では現代仮名づかいに書き改められた。リーダビリティが増したことにより、小説を読む悦びにあふれたこの傑作がさらに多くの人たちに届いて欲しいと思う。
主人公の松嶋真司は国文学を専門とする大学講師である。義父は同じ大学の教授で、将来は約束されているかのように思えた。ところが妻が交通事故で死んだことで義父との仲が気まずくなる。そんな彼のもとに戦後間もなく自殺した小説家、佐脇依彦の未発表手記が持ち込まれ、彼はこの手記を利用して義父におのれを認めさせようと考える。手記の持ち主からは公開の条件として「手記中の謎を解いて欲しい」と依頼され、自殺の原因を追求することになるというのが物語の発端である。
作中に独立した作品を内包している、いわゆる〝作中作〟を取り扱ったミステリは珍しくはないが、作中作が名のある文学者によって書かれているという設定に限れば、天才と呼ばれた歌人の短歌が含まれる連城三紀彦の「戻り川心中」(一九八〇年)や、幻想小説家としての江戸川乱歩が書いた(という設定の)短編が挿入されている久世光彦『一九三四年冬 ―乱歩』(一九九三年)、四世鶴屋南北の脚本が登場する芦辺拓『鶴屋南北の殺人』(二〇二〇年)などはあるものの、それほど多くは見つからない。文学者の作品という設定である以上、作中作にも相応の出来栄えが要求されるせいなのかもしれない。ミステリとしての仕掛けを施すことになると、ハードルがさらにあがる。だが、本書の手記にはミステリとしての企みが潜んでいることはもちろんであるが、死を前にした心情が赤裸々につづられており、私小説を背景に持つ作家が書いたものとしてリアリティを感じる。展開も起伏に富み、単独の作品としても読み応えがある。
手記は、徴兵検査で丙種となり劣等感にさいなまれた佐脇が、戦後に得難い友人と出会い、自分を取り戻すところから始まる。しかし、戦場での怪我がもとでその友人には死期が迫っていた。佐脇は昔の愛人の行方を捜してほしいという友人の最後の頼みを引き受けるのだが、時を同じくして、凡庸な小説しか書けなかった彼が非凡な着想を得て、見違えるような小説を完成させる。作中には佐脇自身が意識している描写はないがタイミングを考えると、それは彼の無償の行為に対する天からの福音のように感じられる。
手記は本書全体の半分近くを占め、ボリュームからみても松嶋のパートと同等の重みがある。『追憶のかけら』は第五十八回日本推理作家協会賞長編及び連作短編集部門の候補となっており、選考委員の北森鴻から「ここまでの長さは必要であっただろうか」と指摘されている。しかし、本書における手記の位置づけは単なる松嶋の行動のきっかけではなく、佐脇の生の記録として独立しているとみるべきであろう。力のこもった手記が丸ごと含まれているからこそ、読者が感じる感情と同じものを松嶋も感じていると実感できる。いわば佐脇はもうひとりの主人公なのだ。
複数の主人公を同じ重みで記述し、時系列に並べる手法は、貫井徳郎が昨年上梓した大河小説『邯鄲の島遥かなり』(二〇二一年)ではスケールアップしている。この作品は百五十年の島の歴史を血縁関係にある十七人の主人公を通して描いた連作形式の長編で、ユーモアにあふれ、ときに悲哀に満ちたエピソードが時の経過とともに地層のように積み重なり、人間の愚かさや気高さとして心に残る。『邯鄲の島遥かなり』では血筋が大きな意味合いを持っているが、本書では手記がその役割を果たしており、手記を読んだ松嶋はリレーの走者として時を超えて佐脇からバトンを受け取る。
佐脇の自殺は五十六年前のことだから、手記に登場する人物はまだ生きているかもしれないと考え、松嶋は調査を進める。善意に基づいて動いていた佐脇と異なり、松嶋は自分の利益のために活動しているという違いはあるが、どちらも探求の物語である。さらに二人とも挫折の経験がある。探求者としては手際が悪く、周囲の人たちの好意に助けられてかろうじて調査を進めるところも同じである。佐脇はともかく松嶋は研究者なのだからもう少し手馴れていてもよさそうにも思える。だが、贔屓目にみても彼はシャーロック・ホームズではない。調査能力はホームズの手助けがないワトソンと似たようなものだ。ワトソンは決して賢いとはいえないが、松嶋も愚かなワトソンである。松嶋と佐脇は明らかに類似の存在として描かれており、自殺という不幸な結末を迎えた前走者の轍を踏むことなく、松嶋は無事にゴールにたどり着けるかという焦燥感がストーリーを牽引する。
この解説では人生につまずいた男の再生物語としての側面を強調しているが、もちろん本書はミステリである。ただ、殺人は起こらない。しかし、提示されている謎は人生を左右するほどの大きさを持つ。読者を誤誘導する仕掛けも手掛かりも丹念に織りこまれている。ミステリ特有の道具立てや名探偵の魅力に頼らず、現実感のある設定とプロットの巧みさで勝負し、さらに終盤の展開が目まぐるしく二転三転するところは連城三紀彦を彷彿とさせる。
ところで貫井徳郎はデビュー作の『慟哭』(一九九三年)以来、どちらかというと深く重く考えさせられる作品が多い印象がある。それに対して本書では、人生に対するシニカルな視点は背後に回り、作者の温かいまなざしが前面に出ており、ほかの作品と読後感が異なることに困惑するかもしれない。だが、そうした作品に比べて本書がとりたてて異色であるとは思えない。
実際には本書にもさまざまな悪感情が描かれている。ただ、そのほとんどが小粒である。ストーリーの核心に触れない序盤から無難な例を挙げると、松嶋と妻の夫婦喧嘩の原因は本書が書かれた年代を考慮すれば、妻が実家に戻ってしまうほどのことだろうかとも思える(特に男性はそう感じるだろう)。さらに別の場面では、敵であると思っていた人間が味方に転じて驚かされるケースも少なくない。
本書における負の感情が比較的こぢんまりとしているのは、普通の人間が日常生活で抱える好悪にそもそも大した根拠はなく、正と負の感情は地続きで、敵意は容易に好意に反転するという考えが根底にあるせいではないか。本書のあとに書かれた『愚行録』(二〇〇六年)では語り手である登場人物が変わるごとに被害者の印象がたやすく逆転し、『乱反射』(二〇〇九年)では日常の小さな悪意が積み重なって思いもよらない出来事につながっている。本書に現れたモチーフがその後の作品で進化しているのを考えると、陽光が注ぐ裏側には影がさしているように、作者にとってみれば暖かい光を描くことと、心に潜む闇をあぶり出すことは大差なく、本書におけるハッピーエンドはオセロゲームが白と黒の攻防を繰り広げた末に、終了後の盤面で白が優勢になっているだけにすぎないようにも感じる。終盤の展開が二転三転するのもそのためであり、どんでん返しのつるべ打ちには必然性がある。登場人物の感情の揺らぎ次第ではさらに一度か二度、コマが裏返ることもあり得るかもしれない。
今回の文庫作品連続刊行プロジェクトにあたって貫井徳郎は『プリズム』について「物事を決めつけるのが嫌いで、多面的な見方を提示することが多い」とコメントしているが、それは本書にもあてはまる。こうした作風の嚆矢が『プリズム』(一九九九年)であると、実業之日本社文庫から刊行されたばかりの『プリズム』の解説で千街晶之が指摘しているので、ぜひ参照していただきたいと思う。
本書は雑誌『月刊ジェイ・ノベル』に二〇〇二年八月号から二〇〇四年三月号まで連載されたのち、単行本が実業之日本社から二〇〇四年七月二十五日に刊行され、その後、実業之日本社のジョイ・ノベルス(二〇〇六年十二月十五日刊)、文春文庫(二〇〇八年七月十日刊)と判型を変えつつ読み継がれてきた。
この作品が書かれてから二十年近くが経過し、その間、さまざまなことがあった。二〇一一年には東日本大震災が起こり、多くの人命が失われた。哀しみの一方で、人と人との絆を実感することができた。そしてここ数年は新型コロナウイルス感染症の蔓延により人と人との距離が物理的に離れてしまうという状況を経験している。
久しぶりにページをめくると、本書に記されている人と人との繫がりや身近な人たちの好意が現実における出来事と結びつき、新たな感動を呼び起こす。これが今、この小説を読む意味だろう。普通に努力する人間が一番尊い。正と負の感情に大きなちがいがないのならできるだけプラスの感情を保ち続けていく。真っ当な生き方を貫き、当たり前のことを当たり前に行い、人生に怯えることなく凜として立ち向かえば、きっと誰かが手を差し伸べてくれる。たとえ自分のなかに解答が見つからなくても、英知は周囲に存在する。作者が発するそのメッセージは本書の中で微妙にかたちを変えながら何度も繰り返され、強く心に残る。そして、この本が与えてくれた勇気をもとに、次は自分がほかの誰かに手を差し伸べる番である。善意のバトンは次のランナーに手渡されていくことを信じたい。



