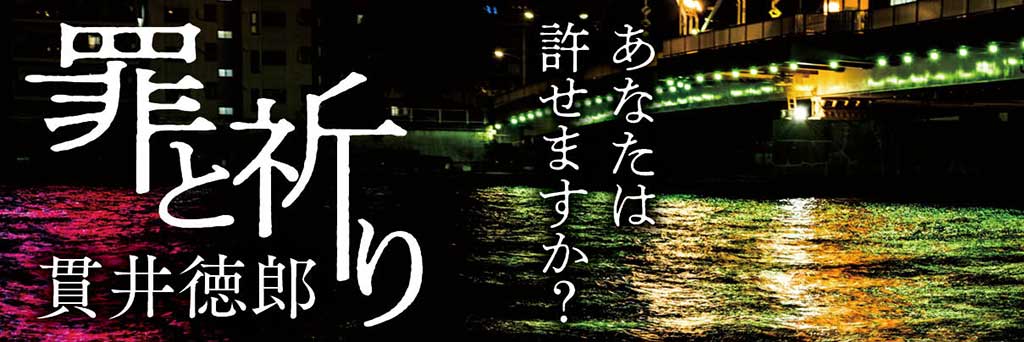
2022年10月文庫新刊 貫井徳郎『罪と祈り』作品解説
親子関係を描いた傑作 西上心太(書評家)
〈おれは、自分の罪から逃げる気はないんだ〉
本書は二〇一七年十二月から二〇一九年二月まで「Webジェイ・ノベル」に連載され、二〇一九年九月に刊行された作品の文庫化である。
書店発売日より前に、書評を扱う新聞社や雑誌編集部などのマスコミ、あるいは書店員や書評家に向けて、新刊書の見本が配られることがある。「プルーフ」と呼ばれる仮綴じのものもあるし、店頭で販売される商品と同じものがあるが、作品のあらすじやキャッチコピーを記した「投げ込み」とか「フライヤー」と呼ばれる、宣伝のためのチラシが同梱されていることが多い。チラシを作成するのはほとんどが担当編集者である。作者と共に生みの苦しみを味わい併走した仲間でもあるから、力のこもったものや工夫を凝らしたものが目立つ。
本書『罪と祈り』親本に入っていたチラシには、作者である貫井徳郎の手書きの一文が大きくコラージュされていた。
「これを書けたから、もう小説家を辞めてもいいです」と。
全力を出し切った自信作。この言葉から筆者はそんなメッセージを受け取った。一読後、その思いは正しかったことが証明された。
警視庁久松警察署管内に架かる新大橋の橋桁に遺体が流れ着いた。見分に足を運んだ同署の刑事・芦原賢剛は、六十歳代に見える男性の遺体を見て驚いた。旧知の人物だったからだ。
遺体は濱仲辰司という元警察官だった。しかも単なる顔見知りではなく、賢剛の家族と深い関わりがある人物だった。辰司は賢剛の父・智士の親友であり、幼いころに父を亡くした賢剛にとって、父親代わりの存在でもあった。辰司の息子の亮輔とは同い年で、兄弟同然に育った仲であり、互いに三十歳を過ぎたいまでも一番の親友である。
最初は誤って川に転落した事故死かと思われたが、側頭部に殴られたような跡があったため殺人事件と断定され、久松署に捜査本部が設置された。賢剛は警視庁捜査一課の刑事と組み、辰司の交友関係を調べる「鑑取り」捜査に従事することになった。
濱仲家も芦原家もずっと下町の浅草に住んでいる。辰司は交番勤務一筋の警察官人生を送り、それを知る地域の多くの者から慕われていた。犯行現場は辰司の自宅からほど近い、隅田川沿いの公園の一角と判明したが、行きずりの犯行の可能性は低く、恨みを買うような人間関係も見当たらず、捜査は難航する。
一方、辰司の息子・亮輔は父の死をきっかけに、自分が父のことをよく知らなかったことに気づく。これまでにも父・辰司が見かけ通りの人間ではないと感じたことが何度もあった。失業中の亮輔は、一週間をめどに父のことを調べようと決意する。父の辰司は生来朗らかな性格だったという。その朗らかさを失ったのは、親友の智士の死――自殺だった――がきっかけだったらしい。遺書も残さず、妻と幼い四歳の息子の賢剛を残し、なぜ智士は死ななければならなかったのか。亮輔は父を知るために智士の自殺の事情を探っていく。
奇数章は現代が舞台となり、息子世代の芦原賢剛と濱仲亮輔の視点で、偶数章は親世代の芦原智士と濱仲辰司の視点で、現代からおよそ三十年近く前の一九八〇年代後半から始まった「バブル時代」を舞台にした、現在と過去の二つの物語が語られていく。
元号でいうと昭和の最末期から平成の初頭まで、五年足らずの時期が「バブル時代」である。ごく単純にいうと、金余りの時代を迎え、その金が投機に向かい、株価や不動産価格が高騰した時代のことだ。もとよりそれは実体経済からかけ離れたものであったが、企業も本業の業績を上げることよりも、不動産の転売――いわゆる土地転がしに狂奔し、銀行もまたその購入資金のため天井知らずの融資を行った。そのため日本全国でマネーゲームが展開されたのである。世間は好景気でわき上がり、新卒を含む就職市場は空前の売り手市場となったものだ。
だが日銀が金融引締めに舵を切ったことなどが原因となり、バブルは弾け株価も不動産価格も下落し、銀行を含む多くの企業が不良債権を抱えることになった。バブル崩壊後は一転して不況となり、後に「失われた十年」と呼ばれるようになる。
このバブル時代の出来事が、この物語のすべての遠因となっている。バブル景気真っ只中の一九八八年。辰司は自分の町内で不穏な出来事が起きていることを知る。辰司が住む西浅草は、盛り場である浅草公園六区からほど近い、古くからの住人が暮らしている町である。この土地でヤクザによる地上げ行為が横行し始めたのだ。しつこい訪問や嫌がらせがエスカレートしていく。だが警察の動きは鈍い。土地開発という「国策」のため、警察は不法行為に目をつぶっているのではないか。辰司は住民と組織の板挟みとなって悩み苦しむ。やがて櫛の歯が抜けるように、土地を売り生まれ育った地元から去って行く者が目立ってきた。不法な地上げ行為の影響で命を失った者も出た。そして土地を売り、豪邸を建てたと揶揄された一家にもある悲劇が起きる。芦原智士は大手不動産会社の行為に憤りを隠せない。智士は彼らに一矢を報いる計画を辰司に打ち明ける。
本書を読んで、バブル景気と昭和の終わり――天皇の死去――が重なっていることに改めて気づかされた。一九八八年(昭和六十三年)九月に天皇の容体悪化が発表されてからの、行き過ぎた自粛騒ぎ、わずか七日で終わった昭和六十四年。一月七日の東京は雪が降りそうな曇り空の寒い日だった。その日の記憶はいまも鮮明である。
その日の午後には後に首相となった小渕恵三官房長官が新元号平成を発表。やがて大喪の礼が二月二十四日に行われることが発表される。
本書の秀逸な趣向は昭和を象徴した天皇を送る日に、ある計画のフォーカスを当てたことにある。智士の先導によって仲間を集め、辰司の考えによって成功する可能性の高い計画が、この日を目指して発動するのだ。
二つの謎によって本書のストーリーは牽引されていく。一つはもちろん辰司を殺した犯人は誰か、そしてその動機は何かというものだ。そしてもう一つが過去に亮輔と賢剛の父親たちが何をしたのか、そしてその顚末はどうなったのかという謎だ。亮輔は警察官として慕われ、柔軟性がある正義感に貫かれた父親に畏敬の念を抱くと同時に、少なからぬ劣等感も抱えている。父・辰司と自殺した智士の足跡をたどることは、辰司が智士の死後に周囲に対して作り上げた壁を壊す作業でもあり、辰司の死後とはいえ、生前に果たせなかった真の親子関係を再構築し、亮輔自身が前に進んでいくことにもつながっていく。
芦原智士は気が優しく、他人に馬鹿にされてもさらりと受け流すが、実は芯が強く肝心な場面で決して逃げず、現実を直視する人間である。そんな智士が罪を犯そうとしていることを辰司は察する。正義が存在するなら、正義の側から悪を断罪するという揺るがない思いを辰司は持っている。だが現実はそうではないことを、地元の地上げ騒動で痛いほど経験し、昭和末期の今は不正義が罷り通る世の中であり、正しさは力の強弱によって決まる世の中であることを知ってしまったのだ。その思いから、智士たちが失敗して罪人にならないように、ついに辰司は彼らに協力することを決意する。
一方の智士も決して自己弁護をしない。
「行動理由がなんであれ、罪を犯すからには許されないことなんだよ。どんな理屈をつけたって、それは許されないんだ。許される罪なんて、あっちゃいけないだろ。罰されない罪があるから、納得できないんじゃないか。おれは、自分の罪から逃げる気はないんだ」
辰司の考えとこの智士の言葉に、本書のテーマが凝縮されている。
義憤から実行された犯罪計画。それによって引き起こされたアクシデントとでもいうべき不幸な悲劇。命を絶った者、すべてを抱え込んで生きてきた者。彼らが犯した罪と、その罪をはからずも掘り起こしてしまった子供たち。
親たちが犯した罪と贖罪の祈り。親たちの過去に対する子供たちの祈るような思い。二つの時代をまたいだ事件を通して、普遍的な親子関係を描いた傑作が本書なのだ。
早いもので二〇二三年は貫井徳郎のデビュー三十周年であるという。衝撃的なデビュー作『慟哭』以来、数々の作品を目一杯の力で送り出してきたのが貫井徳郎という作家である。常に完全燃焼。
「これを書けたから、もう小説家を辞めてもいいです」と宣言するような作品が、これから何作も上梓されるに違いない。



