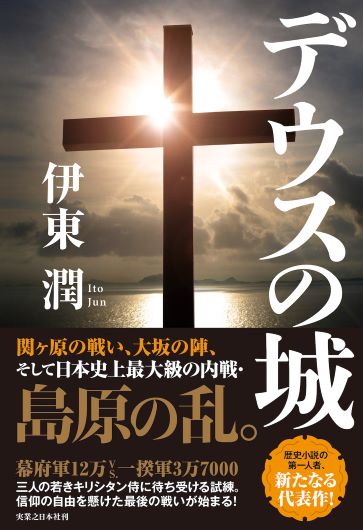伊東 潤『デウスの城』刊行記念 ロング・インタビュー
「本作は私の集大成的作品です」
――大作でしたね。あまりの密度の濃さに、読み終わった後、しばらく放心していました。
伊東:ありがとうございます。自分も書き終わった時は放心状態でした(笑)。これまでの人生で培ってきたもの、すなわち知識、思想、情熱など、伊東潤を構成するすべての要素を本作に叩き込みました。
――これだけの壮大なテーマに挑まれたことに感服しています。しかも見事なストーリー・テリング力で、読み手を摑んだら放さない筆力には恐れ入りました。
伊東:物語に熱中し、読み終わったら多くのものを得ていたというのが小説の妙味の一つです。面白いだけの小説なら世の中にいくらでもあります。しかしそれを読むだけでよいのでしょうか。せっかく時間を使って読書するのですから、生きる上での血肉になるものを得ようとすべきです。その点で本書は、ストーリーを楽しみながら宗教と信仰にまつわる様々な知見を得られるので、得るものも多いと思います。それはまた「考える読書」の一助となり、そうした「実のある」読書を繰り返すことで、自分なりの考えや人格が形成されていくのです。
――執筆にあたって膨大な文献にあたったようですが、執筆前の準備もたいへんだったでしょうね。
伊東:これだけの壮大なテーマに挑むとなると、知識の仕込みがたいへんでした。キリシタン史関連の研究書はもとより、宗教全般についての読みやすい新書や、友人から勧められたものを読みまくりました。そして自分なりに、「宗教とは何か、信仰とは何か」を突き詰めて考えていきました。
また執筆にあたって、自分の中に澱のように沈殿する悪い感情の放出にも努めました。連載開始前の2021年には伊勢神宮にもお参りしてきました。それで心を清めてから連載に取り掛かりました。
本来なら教会に行くべきだったのですが、私はクリスチャンではないので、伊勢神宮に詣でることで「みそぎ」としました(笑)。こうした準備段階を経て、ようやく連載開始となりました。
――執筆にあたって、かなり神経を使われたようですね。
伊東:もちろんです。宗教や信仰というデリケートなテーマですから、キリスト教を信じている人を傷つけないよう、細心の注意を払いました。仏教も同様です。
ただ忘れないでいただきたいのは、何事も頑なになってはいけないということです。信仰心を持つことは大切ですが、世界には自分とは別の宗教を信じる人もいるのです。彼らの気持ちを慮り、受け容れる寛容さを持つことで、世界はもっと住みやすくなると思います。
――しかし本書の根源的テーマとなる「キリスト教は、なぜほかの宗教を否定するのか」という問題とは、真逆の考え方ですよね。
伊東:そうとも言えません。最近のローマ法王は活発に他宗教のトップと会談しています。これは他宗教を頭から否定せず、それぞれの立場や考え方を認め、世界平和という共通した目標に向かっていきたいという法王の思いの表れだと思っています。つまり宗教界は二十一世紀になり、たいへんよい方向に進んでいると思います。
そうしたことも踏まえ、本作では「一神教」というナーバスなテーマにも斬り込んでいます。私の「一神教」に対する解釈が正しいかどうかは別にして、キリスト教を語る上で避けては通れないテーマですからね。
名作『沈黙』に挑む
――そうした高いハードルを設けながらも、これだけリーダビリティの高い作品に仕上げられたのはさすがです。本作を書こうと思ったきっかけは、何だったのですか。
伊東:これまでも、戦国時代の茶の湯、室町時代の経済、江戸時代の学問、戦犯問題、学生運動、戦後沖縄といった、あえて難しいテーマに挑んできた私ですが、さらに難しいテーマに挑むことが、作家としての自分を成長させることだと思ったからです。これまで書いてきた戦国武将物などの手慣れた方向に流れてしまえば、それで作家としての成長は止まります。だからこそ最難関とも言える宗教に挑まねばならなかったのです。ただし本作も通過点にすぎません。本が出せる限り、これからも様々な挑戦を続けていくつもりです。
もちろんそれだけではなく、「宗教とは何か」を探求したいという知的好奇心もありました。作家というのは、その時に「探究したい」題材を選ぶものです。そして自分の知ったことを絞りに絞り、本質部分を分かりやすく読者に伝えていく。それが小説の使命の一つだと思っています。

――これまでこの時代のキリシタン信仰を描いた小説としては、伊東さんも「挑む気持ちで書いた」と常々仰せになっていた遠藤周作氏の『沈黙』がありますが、いかなる気持ちで挑んだのでしょうか。
伊東:『沈黙』は傑作です。しかも名匠マーティン・スコセッシ監督によって映画化されたことで、いっそうの輝きを放つことになりました。この燦然たる高峰に私ごときが挑むのは僭越ですが、そのくらいの気概がなければ、購買読者に対して失礼です。
『沈黙』のテーマは「神はいるのか」という壮大なものです。それは、キリスト教徒である遠藤周作氏が終生追い求めたテーマでもあります。それに私のような門外漢が挑むには、キリスト教関連の史料や関連書籍を読み込み、自分なりの宗教観を確立させてからでないと失礼だと思いました。
――『沈黙』もそうですが、これまでのキリシタン関連の小説の大半がそうであったように、「キリシタン=いい人」「弾圧する幕府側=悪い人」という図式を壊し、幕府側の言い分もしっかり書かれていますね。
伊東:そうした平衡感覚こそ小説には大切です。「弾圧する側の言い分なんて聞きたくない」という人もいるでしょう。しかし史実から目を背けてはいけません。キリスト教は一神教ゆえ、時に暴発することがあり、それが神社仏閣の破壊、また僧侶や神官の殺害に結び付いていったのも事実なのです。また宣教師たちは殉教を賛美しますが、「殉教のどこが美しいのか」という私自身の思いもぶつけました。
――つまり伊東さんは、キリスト教と仏教のどちらにも偏らない平等な気持ちで書いていったのですね。
伊東:作家にとって大切なことの一つに客観性があります。誰でも好みはあります。例えば好きな武将もいれば、嫌いな武将もいるでしょう。しかし先入観や固定観念で好悪の情を抱くのではなく、その人物の事績などを調べ上げ、客観的に評価することがプロの仕事だと思います。それは宗教も同じです。当時のキリスト教、主にイエズス会の功罪についても是々非々で描けたと思っています。
――視点人物の心中なども、伊東さんの思想や考えではなく、彼らが考えそうなことを描いていったということですね。
伊東:そうです。本作では、キリスト教とそれを取り巻く当時の人々の心中を余すところなく描き出しました。文中に出てくる人物や小さなエピソードも、大半は実際にあったことをベースにしています。
小説とは自分の思想や考えを述べる場ではなく、登場人物の立場を踏まえ、その迷いや葛藤を彼らの視点で描いていくものです。ですから登場人物たちの考えが、すべて作者の考えと一致するわけではありません。ここのところを誤解する人が多いので、いつも困っています。
――作中では、『沈黙』でも重要なパートを担っていたフェレイラ神父が登場しますが、まさに迷い苦しみながら、自らに「信仰とは何か」を問いかけていますね。
伊東:僭越な言い方ですが、『沈黙』では、フェレイラ神父の苦しみが少し伝わりにくかったと思います。それを本作では自分なりに解釈しました。もちろんこれは私の解釈ですから、「それは違う」と指摘されれば、「そうかもしれませんね」としか答えられません。
そもそも歴史小説とは作者の歴史解釈なんです。一次史料と定説を吟味し、自分なりの解釈を下していく。そして、それを物語に乗せていくのが歴史小説なんです。ですから本作のフェレイラ神父は、こうした作業を経た上での私の解釈です。
――映画『沈黙』には、特別の思い入れがあるようですね。
伊東:私が兄のように慕っていた頭脳警察のパンタさんが重要な役割で出演していたことで、映画版『沈黙』には特別の思い入れがあります。残念なことにパンタさんは、今年すなわち2023年の7月に73歳で他界しました。
ロケはオーストラリアで行われ、もちろんパンタさんも行ったのですが、その時の楽しい逸話もたくさん聞きました。とくにパードレ・ガルペ役のアダム・ドライバーと仲よくなったらしく、二人でいろいろ悪戯をしていたようです。パンタさんとの出会いや仲よくなったきっかけについては機会を譲りますが、そんな御縁もあり、映画版『沈黙』は、つごう五回は見ていると思います。
「三位一体」――三者三様の視点で描く
――本作は、駒崎彦九郎範茂、日吉善大夫元房、松浦左平次重能という三人の架空の人物の視点が交互に出てくる構造になっていますね。三人三様の生き方を描きたかったのだと思いますが、その真意はどこにあるのですか。
伊東:キリスト教には「三位一体」という言葉があります。「三位一体」とは、全く異なる三つの様相が、その本質においては一つだという意味です。そこから三人の視点を交互に出していくというアイデアが浮かびました。同じような環境に生まれた三人ですが、運命の悪戯によってか、別々の道を歩むことになりました。しかし最後には、別の二人が自分の別の一面を映し出していることに気づきます。つまり一つ間違えば、自分もほかの二人と同じ決断を下し、彼らのような道を歩んでいたかもしれないことに気づくのです。三人の中には信仰を貫けた者もいます。しかし彼は傲然と胸をそびやかしているわけではありません。残る二人の立場に共感するのです。
卑近な例を挙げれば、会社や学校で、誰でも嫌いな人や気が合わない人はいますよね。しかしその人は自分の映し鏡でもあるのです。つまり「人の振り見てわが振り直せ」という格言にある通り、自分も一つ間違えば彼や彼女のようになっていたかもしれないのです。自分も彼らと同じようなことをしていないか、同じような一面があるのではないかと考え、彼らに共感していけば、人間関係は好転していくものです。そして彼らを見て、自分の悪いところを直していくことが大切なのです。
――本作は、三人の登場人物の視点が交互に登場する「多視点構造」になっていますね。
伊東:これまでも多視点群像劇、二人の視点スイッチ、または四人の視点スイッチという手法をしばしば使ってきましたが、三人は初めてでした。
どうして視点をスイッチさせるのかというと、何かの事件があった際、異なる視点から捉えられるからです。本作の場合、立場を違えていく三人の視点から、特定の事件に対する、それぞれの思いを述べさせている部分がありますが、そうした点からも三人視点が正解でした。それだけキリシタンをめぐる諸問題は多面性があり、一概に善悪の判断がつけにくいのです。

読者をその時代に連れていく
――本作では、実在した人物と架空の人物が交錯しながらストーリーが進んでいきます。こうした手法は伊東さんの得意とするところですね。
伊東:後景で実際の歴史が流れ、前景で架空の登場人物たちが活躍するという構造ですね。そして実在と架空の人物が互いに歩み寄り、縦糸と横糸のように交錯し、タペストリーのように物語が紡がれていくという手法です。歴史小説には以前からある手法ですが、本作では、この手法の必然性がよく分かると思います。こうした手法一つにも、作者の意図が込められていることを洞察してほしいですね。
――登場人物の中で気に入っている人は誰ですか。
伊東:千々石ミゲルとトマス荒木ですね。彼らは背教者と呼ばれてきましたが、キリシタンであることを捨てていません。彼らはイエズス会の教えについていけず、イエズス会を脱会した宗教的孤立者なのです。つまり布教と侵攻が一体となっているイエズス会に嫌気が差したのです。それをイエズス会側は背教者扱いしているのです。
――金地院崇伝や南光坊天海といった仏教界の大物も、しっかり描かれていますね。
伊東:この機会に、二人についても詳しく調べたところ、そこには野心や腹黒さなどなく、自分に課せられた仕事を黙々とこなしている姿が浮かび上がってきました。天海は少々微妙ですが(笑)、少なくとも崇伝は僧侶というより学者兼官僚なので、極めて真面目な人だったようです。本作では、そんな彼らの実像を伝えていきたいという思いもありました。
――本作では、冒頭が関ヶ原で、ラストが原城攻防戦のシーンですね。
伊東:読者が物語に入りやすいので、関ヶ原のシーンを物語の起点としました。ラストは原城攻防戦ですが、この戦いでキリシタンの勢力が著しく衰えるので、それしかないという思いがありました。ちなみに『沈黙』は、この後の時代を描いています。
また本作のテーマとは別ですが、これまで私は、戦国時代の大合戦を描き続けてきました。ちょうど昨年『天下大乱』で関ヶ原の戦いを、『一睡の夢 家康と淀殿』で大坂の陣を描きましたが、本作で取り上げた原城攻防戦で、戦国時代から江戸時代初期にかけての三大合戦を描くことができました。それはそれで感慨深いものがあります。
――今回も「読者をその時代に連れていく」ことを心がけているのが、よく分かりました。
伊東:小説というのは旅行なんです。自分の部屋にいても、本を開くだけで別の世界に連れていってくれる。それが小説の素晴らしさの一つです。本作を書くにあたっても、江戸時代初期の長崎、島原、天草地方の状況をよく調べ、現地にも取材に行きました。やはり現地の空気を吸ってこないと、読者をその場にお連れすることはできません。
島原や天草に行ってみて最も感銘を受けたのは海の青さですね。「そんなことは当たり前だろう」と思われるかもしれませんが、有明海を様々な角度から眺めてみて、初めてキリシタンたちの気持ちが理解できた気がしました。あの青い海なくして、あれだけ真摯な信仰心は育たなかったと思います。
作家・伊東潤の集大成。そしてこれから…
――ところで、伊東さんご自身は信じている宗教がありますか。
伊東:私は無宗教です。強いて言えば伊勢神宮を信仰しています。というのも2018年に初めて行った時、お参りを終えて階段を下りている時、胸のつかえがすーっと消えていった気がしたのです。それまでの人生で溜め込んだ悪い感情が、その時に一掃された感がありました。しかし生きていると、またそうしたものが積もってくるので、前述のように、本作の連載開始前に、もう一度行ってきました。
キリスト教に関しても全く偏見はありません。これまで御縁がなかっただけです。
たまたま今年の9月、伊豆の「川奈ステンドグラス美術館」というところに行ったのですが、展示品がたいへん多く、パイプオルガンの演奏まである本格的な美術館でした。そこで改めてキリスト教文化や美術の素晴らしさに触れることができました。こうした経験から、キリスト教の作り上げた世界観に感動し、もっと知りたいという気持ちが湧きました。また何かの機会があれば、キリシタンに関する小説を書くかもしれません。
――いよいよ『デウスの城』が刊行されるわけですが、今どんな思いでいますか。
伊東:本作は私の集大成的作品です。まだ心身共に健康なので、作家・伊東潤の道は続きますが、これで折り返し点を回った感があります。これからは、今まで以上に書きたいものを書いていくつもりです。
また常々言っていることですが、もう一つの目標として、通史を小説として描いていきたいという思いもあります。まだまだ長い道のりですが、そうした大きな目標を持つことで、作品を書くというモチベーションや作家としての緊張感が保てると思います。
――本作も、さすがとしか言えない筆致で楽しませていただきました。最後になりましたが、読者へのメッセージをお願いします。
伊東:作家にとって大切なのは志と大義です。もちろん作家といっても様々ですから、そうしたものがなくても活動できる方もいらっしゃいます。ただし私は、死ぬまで志と大義を掲げていきたいのです。「金のために書いている」とニヒルぶっている作家たちに冷笑されようと、私は自分の志と大義を掲げ、自分の道を突き進むだけです。
それゆえ私の創作・執筆姿勢に共感していただける方は本を買って下さい。その一冊が私の作家活動を支え、それによって生み出された作品が、次の世代の萌芽へと結び付いていくのです。作家の活動は、読者の皆さんに本を買ってもらうことによって成り立っていることを忘れないで下さい。