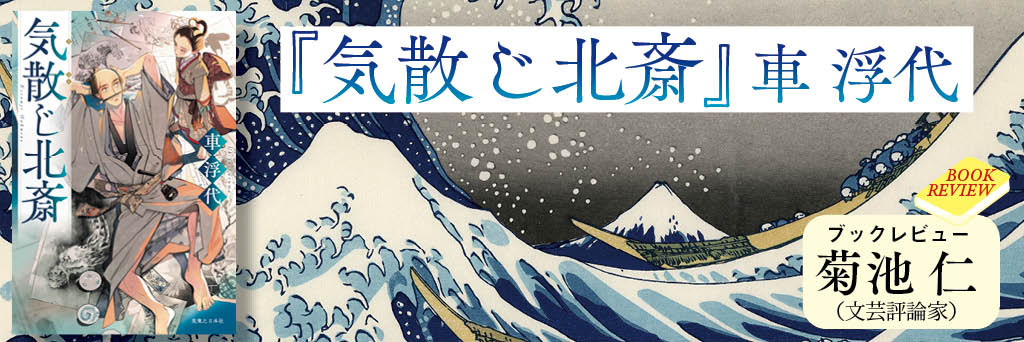
2024年2月の新刊 車浮代『気散じ北斎』ブックレビュー
巧みな構成と斬新な設定で迫る北斎と娘・応為親子の驚愕の真実とは? 菊池 仁(文芸評論家)
確信していることがある。作家は書き出しの文章に神経を使う。それだけに書き出しが面白いかどうかが、作品の成否を決めるといっても過言ではない。その点で本書は間違いなく傑作との邂逅を期待させる。
作者は葛飾北斎の生涯を描くにあたって、数え三十六歳の北斎と継娘となる六歳のお栄(後の応為)との出会いの場面から筆を起こしている。この出会いこそ車浮代版北斎像の底流を象徴するもので、それを裏付ける格好のエピソードを用意している。お栄が初めて筆を使って描いた絵の稽古の筆使いを目にした時に、「――こいつは……とんでもねえや! 恐るべき天分を秘めた娘――。」と北斎が感嘆する場面である。北斎はそこに初めて筆を持った六歳時の自分を重ね合わせていたのだ。物語は六歳の北斎に戻り、絵画修業の遍歴のスタートとなる貸本屋に奉公するまでのエピソードへと続く。その後も、章の冒頭でお栄との交情の密度を描くことに費やし、物語を引っ張る太い動線となっている。
作者は、大阪芸術大学デザイン科を卒業、浮世絵と江戸食文化に造詣の深い評論家としても活躍している。本書は、そんな作者が浮世絵研究の成果を踏まえた独自の見解と人物解釈を起爆剤として、北斎と応為の新たな人物像に迫るというモチーフで取り組んだ作品である。その意欲がこの巧みな構成で表現されており、第一の読みどころとなっている。
第二の読みどころは、北斎と応為の特異な親子関係に照準を合わせたことである。北斎と応為を描いた先行作品は杉浦日向子『百日紅』、朝井まかて『眩』など数多くあるだけに、差別化をどう図るかがポイントだ。
そこで作者が工夫を凝らしたのが、北斎とお栄の出生に絡めたある驚愕のエピソード、そして北斎と応為の親子関係の変化の内実を克明に描くことであった。例えば第二章で作者は、お栄が実父から暴力を振るわれた経緯を綴っている。その事実を知った北斎は憤り、「俺は一生を賭けてお前を守ってやる」と言う。その日から北斎はお栄の全てとなった。つまり、北斎とお栄は血のつながらない親子という設定なのだ。本書の二人の特異と見える親子関係のコアとなっている。
第四章では、十九歳となった応為が北斎と共に画業に専念し、ずば抜けた才能を発揮する姿が登場する。北斎は、お栄の描く絵は、いくつもの流派を渡り歩き修業してきた自分と違い、本物の天才と確信している。しかし、お栄は絵を描くこと以外の生活全般には全く関心を示さない。北斎は将来を慮り葛飾応為という雅号を与え、嫁に出すが、作者の狙いは応為の絵師としての業がどんなもので、どこへ行こうとしているかを暗示するところにある。この受けがラストの北斎死後の応為を描いた第六章となる。
第三の読みどころは、北斎の絵画修業の遍歴を成長の中核として、技法習得の過程を克明に描いている点である。更に、その栄養素として、蔦屋重三郎、喜多川歌麿、東洲斎写楽等の一流人との交流を取り入れたことである。ただし前提がある。北斎の生きた時代は、町人社会が経済的実権を獲得し、それを足場に活力に満ちた新鮮な創造的エネルギーを発散させ、武士階級とは違う独自の文化を形成。特に浮世絵、黄表紙、歌舞伎などの大衆文化の隆盛には目覚ましいものがあった。つまり、北斎はこの時代の申し子的存在と言えよう。
絵画修業の遍歴を見ていく上で際立っているのは、北斎が出世魚のように名前が変わるたびに技法を豊かなものとして成長していることである。例を挙げよう。鉄蔵時代に貸本屋に奉公し、その後、彫師修業をしている。これが浮世絵へのあこがれとなる。晴れて勝川春朗として浮世絵絵師となるが目が出ない。そんな春朗を救ったのが蔦屋重三郎であった。蔦屋に物事を逆から見るという考え方があることを教わる。これが技法に活かされていく。
俵屋宗理時代には写楽との出会いがあり、作者は写楽が何者なのかという大いなる謎に挑戦し、綿密な時代考証に基づいた、独自の答えを用意している。そして四十二歳の時、北斎に改名する。これは北斎が自分自身の世界を独自に表現できるという揺るぎない自信を持ったからに他ならない。出世魚はさらに高みを目指して前人未到の境地を求め、絵との格闘を続けていくのである。
第四の読みどころは、葛飾応為五十半ば、これまで気散じ(心の憂さを晴らすこと)もなく絵に邁進してきた北斎が八十五歳となった第六章で、信州小布施の旅で幕を開ける。一転して作者の筆勢は穏やかなものとなる。浮世絵を極めるためそれぞれの狂を生きてきた二人の静謐な佇まいがそこにある。二人の魂の結びつきがますます強固になっている証左だ。そしてラスト、応為が父・北斎への思いを語る場面は感動的である。
本書はまさに作者の最高傑作であり、一級のエンターテインメント作品に仕上がっている。



