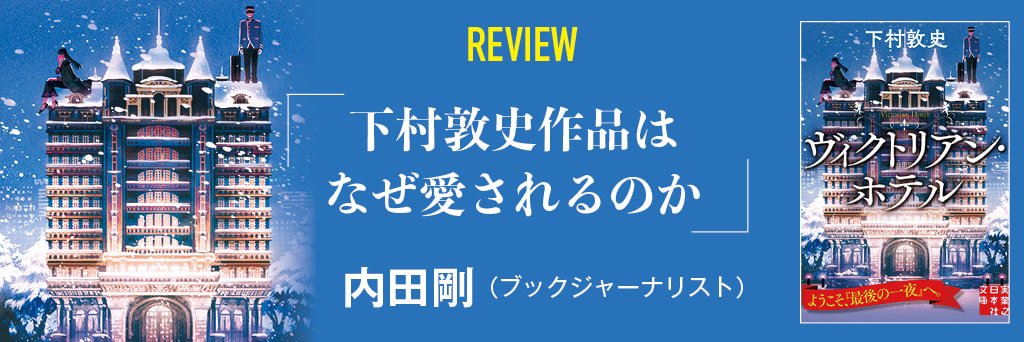
『ヴィクトリアン・ホテル』ロングヒット記念
下村敦史作品はなぜ愛されるのか 内田 剛(ブックジャーナリスト)
下村敦史さんの『ヴィクトリアン・ホテル』の文庫版は、2023年2月の刊行以来ロングセラーとなっています(2024年10月現在9刷)。この冬は、雪が舞い散るイラストを装画担当のいとうあつきさんに描きおろしていただき、「冬バージョン」のカバーが書店店頭を彩る予定です。下村作品が愛される理由を、デビュー当時より書店現場から応援を続けてこられた内田剛さんが紐解きます。
下村敦史作品には、読む者を引きつける特別な魔力がある。どの物語を読み終えても
「いてもたってもいられない」気持ちが抑えきれなくなる。
そのピュアな感情は、書店員であれば「売りたい!」に、編集者であれば「何が何でも
この面白さを伝えたい!」に、読者であれば「誰かに教えたい!」となる。つまりは拡散しないと落ち着かない気分になるのだ。下村作品の「沼」に一度ハマれば後戻りできない。これは関係者や下村ファンたちの共通の思いだ。
まったく出し惜しみをせずに、読者をとことん楽しませるサービス精神。それが下村作品の魅力だ。引き出しの多さと深さには、ただただ唸らされるばかりである。そして作品もさることながら、著者ご本人もまた魅力にあふれている。会えば誰もがその人柄の虜となること間違いなし。書店員からの支持が絶大なことも頷ける。
2014年に『闇に香る嘘』で江戸川乱歩賞を受賞しデビュー。しかし4回の最終候補作での落選があっての受賞ということでも話題となった。こうした下積み時代に培った努力がデビュー後に花開いたのであろう。アイディアの豊富さと、テクニカルな部分での切れ味、これが本当に群を抜いていた。
下村作品をそして本人を知れば誰もが「チーム下村」の一員だ。書店員と出版社がそれぞれにアイディアを絞って、連携をしながら様々な取り組みを行ってきた。例えばデビュー作『闇に香る嘘』の文庫化の際に、出版社が持ってきたのは、こう言っては悪いが平凡な販促物であった。これでは作品の持つ強烈なインパクトがまったく伝わらない。
たまたま集まっていた書店員たちに意見を聞いて、最終的には漆黒の全面オビが出来上がった。この物語の主人公は盲目の人物なのだ。今でこそ店頭には「黒帯」も珍しくないが、当時、全面黒は画期的だったのではないだろうか。さらにはある売場の担当者は、その「黒本」をシュリンクして黒い箱に入れて販売。お客様に暗黒の世界を体験するような仕掛けを用意した。物語の持つ衝撃を書店店頭でも再現したのである。
また、臓器移植をテーマとした『黙過』の発売時には、心臓の模型を拡材にして店頭に置いた。右も左も「映え」の時代である。立ち止まらせるためには、もはや言葉はいらない。一目で分かるビジュアルを重視したのだ。用意した出版社の話によると、おぞましい臓器がズラリと会社の机の上に並び、トラウマになるくらい壮観であったという。
3年ほど前に小説紹介クリエイターのけんご氏にインタビューをした際に、「新しいアイディアの特殊設定ものを読みたい」という話があった。間違いなく現在の読者は新たな刺激を求めている。コスパ、タイパを何よりも価値観の中心とする世代。極限状態のミステリーが時代の潮流を作っているが、こうした現在の空気のど真ん中に下村敦史がいることは間違いない。
そのけんご氏の新刊『けんごの小説紹介 読書の沼に引きずり込む88冊』の中でも「前代未聞の小説」と絶賛されている『同姓同名』も記憶に新しいベストセラーだ。犯人も被害者も全員同じ名前とは、よくぞ考えつくものだ。たとえ思いついたとしても、このアクロバティックなテーマを破綻させずに上質なエンターテインメント作品に昇華させるとはまったく信じられない。
『同姓同名』の勢いは著者作家デビュー10周年記念作品である『全員犯人、だけど被害者、しかも探偵』にもつながっている。今度は、「登場人物全員が犯人で被害者で探偵だった」とは。設定を聞いて気にならない読者はいないだろう。密室に閉じ込められたのは社長殺しの疑いのある7人。犯人だけが生き残れる奇妙なミッション。毒ガス噴出までタイムリミットは48時間。何たる心臓破りの狂気だろう。暴かれた人間の素顔と著者の企てが恐ろしい。密室ミステリーに見せかけた、180度違うエンタメミステリー。まさに一冊丸ごと「どんでん返し」のような際立つテクニックを堪能できる。
どんでん返しのほかに、下村作品を語る上で重要なワードは「建築」だ。まずは『ガウディの遺言』に注目してみよう。そのタイトル通りスペインの巨匠アントニオ・ガウディの謎に迫った衝撃の一冊。物語はサグラダ・ファミリアの尖塔に吊るされた死体という冒頭のシーンから引きこまれる。事件の真相には幻の設計図をめぐる禁断の事実が隠されていた。不慮の事故で母を奪った因縁の地・バルセロナを舞台に、事件発生と同時に行方不明になった父。その父との葛藤をかかえながら危険を顧みずひたすら謎を追う娘。心理的なスリルを存分に味わえる建築ミステリーであり、心を揺さぶる家族小説に仕上がっている。
そして『ヴィクトリアン・ホテル』も下村作品の傑作の森の中でも、もっとも印象深い物語のひとつである。100 年の歴史があるホテルの「最後の一夜」を舞台にした、グランドホテル形式の長編ミステリーで映像が浮かぶ描写も見事。ひとつの建物に集まったさまざまな人生が交錯し、虚と実、善と悪、絶望と希望といった相反する要素が絶妙に溶けあって、深い闇の中から眩しい光を掬いとる極上の群像劇なのである。
『ヴィクトリアン・ホテル』は2023年2月に文庫化されたが、発売から1年半以上経っても版を重ね続けてロングセラーとなっている。単行本の発売時にはホテル仕様のメッセージカードが、文庫には、ほぼ文庫サイズのペーパークラフトが販促物として用意され、店頭でも読者を立ち止まらせた。出版不況といわれる昨今、本の寿命が短くなっているのだが、そんな中で工夫を凝らしながら長く売るというのは並大抵なことではないのである。
下村敦史が自宅を設計中に執筆していたのが、この『ヴィクトリアン・ホテル』だ。下村邸のマスターベッドルームはヴィクトリア調で統一され、まさに作中のホテルのような空間イメージ。下村邸はこのほかにも、螺旋階段、ロココ調のサロン、謎解きが必要な秘密の地下室など、ミステリー作家が「誰かを驚かせたい!」という想いがぎっしり詰め込まれた夢の洋館。オーディオルームやゲストルームまであって、日常を忘れさせてくれるテーマパークなのである。
さらなる驚きは、この下村邸をそのまま舞台としたミステリー作品『そして誰かがいなくなる』に登場したことだ。作中には邸宅の写真や図面も掲載されており、「そこまでやるか」の連続である。完全なる密室である作家の豪邸に集められた出版関係者。次々に明かされる盗作の疑惑に文学界の闇。周到に用意された罠に驚愕必至の物語だ。まさに「館」ものの新たなスタンダートにして、この著者にしか描けない「唯一無二」の一冊なのである。
建築にはロマンがある。人間の日常の営みを支える学問であれば、絵画、音楽、文学、哲学といった、人を人たらしめる思考を収斂させた壮大な芸術である。そんな建築をこよなく愛する下村敦史はロマンチストに違いない。どんなブラックな作品にも揺るぎない人間愛が感じられる。だから読後の余韻が素晴らしいのだ。
日頃あまり本に親しんでいないビギナーでも、熱心なミステリーファンでもどちらでも楽しめるのが下村文学だ。これからどんなスリルと出合えるのだろうか。「どんでん返しの魔術師」による新たなサプライズを期待しよう。



