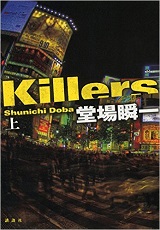著書100冊突破記念トークショー
作家・堂場瞬一を読み解く5冊 聞き手 大矢博子
本と街をつなぐイベント「ブックマークナゴヤ2015」で、トークショー「堂場瞬一の◯◯な5冊」が開催されました。多岐にわたるテーマで執筆された100冊から「これを読んだら堂場瞬一がわかる、もっと楽しめる」作品を厳選、書評家・大矢博子氏が堂場ワールドの魅力に迫りました。
構成・写真/ジェイ・ノベル編集部

自分自身が読みたい
スポーツ小説を書いている
大矢: 今回初めて名古屋にいらしたとうかがいました。"名古屋メシ"はもう召し上がりましたか。
堂場: 52歳にして名古屋初体験です。昨日午後に名古屋入りして書店まわりをしたあと、とりあえず本場の小倉トーストを……とコメダ珈琲店へ。夕食では味噌カツもきしめんも食べましたし、今日のお昼は味噌煮込みうどんに行ったので、半分くらいは名古屋メシを体験したことになりますね。
大矢: 硬かったでしょう、味噌煮込み。
堂場: まさに、アルデンテでしたね(笑)
大矢: 堂場さんはこの夏以降、96冊目から100冊目まで、つづけざまに新刊を出し、刊行されたばかりの『Killers』で著書100冊目に到達されました。警察、スポーツを柱に、幅広く展開する堂場ワールドですが、事前にご本人と周囲からの推薦作品を挙げてもらいましたので、その話を中心に進めて参ります。
まずは、担当編集者代表オススメの一冊から。野球小説の『ラストダンス』
堂場: 今季のプロ野球はベテラン選手の引退が相次いでますが、ちょうど重なるような話ですね。実はこのタイトル、バスケのマイケル・ジョーダンにちなんでいます。ジョーダンの二度目の引退のとき、最後のシーズンを「ラストダンス」=毎試合が最後のお祭りと称したんです。
大矢主人公は二人。プロ野球チーム「スターズ」のベテラン捕手と、一時代を築いた投手。同期入団で、ともに今季限りの引退が決まっているんですね。
堂場: 二人が、最後の試合でいやいやながら、初めてバッテリーを組むことになる。
大矢: その試合はチームの優勝がかかっていて、投手はなんと完全試合を目論んでいる。さて、どうなる……というお話です。
堂場: 水島新司さんでも書かないような展開ですよね。「スターズ」というチーム、実は何度か出てきているんです。最初が『焔(ほのお) The Flame』、次が『ラストダンス』。
大矢: 引退後の二人が『20』では、監督とコーチになって登場しています。
堂場: 「スターズ・クロニクル」として、これからも書いていきたいですね。
大矢: 堂場さんの野球小説は、状況は漫画的なのに、プレーの描写や試合の展開はとてもリアルで説得力があります。現実の試合を見てるみたい。
ところで、高校野球を描いた『大延長』以外は、ピークもしくはピークを過ぎた選手ばかりを扱っておられます。何か意図はあるんですか?
堂場: 肉でも果物でもそうですが、人間も腐りかけの直前に絶頂期がきます。ピークを過ぎようとするとき、その人がどう踏みとどまるか、もう一歩上にいくのか、そういうところを書きたいと思っています。
大矢: 大人のスポーツ小説、ですね。
堂場: 僕自身が読みたいスポーツ小説が少ないんですよ。52歳にもなって高校生の爽やかな成長小説じゃないな、自分で読めるものを書きたいな。となると、自ずと大人が主人公になってくるわけです。
大矢: 続いて、書店員さんオススメの一冊『チーム』 。箱根駅伝・学連選抜チームのお話です。箱根駅伝の出場チームは20校。前年10位以内だとシード校になり、残る10チームは予選会で選ばれます。「学連選抜」は予選会でも敗れた大学の中から個人記録が上位の選手を"寄せ集めた"チームなんですね。
堂場: 2003年に始まった学連選抜が2008年に4位になった。これは使える、こいつらに優勝狙わせてもおかしくないな、と。その時にチームを率いていた、今年の優勝校・青山学院大学の原監督にもインタビューしました。
大矢: いまはオープン参加の「関東学生連合」に変わりましたけど、以前は公式記録にも残り、学連選抜が10位以内に入ると、翌年シード枠がひとつ減る、つまり後輩に出場のチャンスを残せたんですね。
堂場: とはいえ、自分の大学で出場するわけではない。どんなモチベーションで走ればいいのか。そもそも駅伝は日本にしかない、きわめて日本的な競技なんです。駅伝にチームワークは必要なのか。自分が一番早く走ればいいだけじゃないのか……ずっと抱いていた疑問をぶつけた作品です。
大矢: 駅伝・マラソン小説は、ひとつのシリーズになっていますね。ドーピングがテーマの『キング』が最初でした。
堂場: 私は必ずしもドーピング否定論者ではなくて。やって死んでも自己責任でしょう。でも、死ぬかもしれないのに、どうしてやるのか? そこまで勝つことが大事なのか。人間の根源的な欲望とは……もやもやしながら書きました。
大矢: 五輪男子マラソン代表、最後の一枠に挑む、タイプの違うランナー三人が出てきます。選考レースを控え、優勝経験のないランナーの前にドーピングをすすめる謎の人物が登場するというお話ですね。
堂場: レースシーンが全体の10分の1しかなくて、スポーツ小説というよりサスペンスに近いんですけどね。
大矢: この次が『チーム』で、両作品の登場人物がつながるのが『ヒート』ですね。
堂場: 最近のマラソンって、日本人選手はタイムがでないじゃないですか。そこで「世界最高を狙わせる」レースを作ったらどうだ、と考えた。コース設定とかレースの運営で世界新を狙えないか、と。
大矢: 読みどころのひとつは、主人公がペースメーカーというところですね。30キロ過ぎで走るのを止(や)めねばならないランナーのモチベーションにも注目。
堂場: もうひとつは、私の作品中もっとも傲慢なキャラクター、山城くんでしょう。山城に世界最高を出させたい。そのために周りの人間が陰謀を企んだのです。
大矢: そして最新刊『チームII』 。怪我と所属チーム廃部の危機で引退の瀬戸際に立つ山城がどうするか、という話ですね。
堂場: 公務員ランナー川内くんのように、個人でやらせる方向もあったでしょうが、周囲が山城を放っとかない。なんとかしてやらなきゃ、とお節介を焼く、べたべたな物語です。
大矢: 堂場さんのスポーツ小説って原則、爽やかな感動路線ではないんです。なんだけど『チームII』では図らずも、「うそ! 堂場瞬一に泣かされるとかありえない」と思いながら、ポロッときました。
堂場: 普段は当たり前の感動にもっていかないようにしていますが、これは最初から狙ってました。
大矢: ところで本書は冒頭いきなり、レースが終わった場面で始まりますね。
堂場: 実は『ヒート』のラストで誰が勝ったか書かず、大批判を受けまして。どっちでもよかったんですけど(笑)。なので、その結末をプロローグとして書きました。
大矢: 『神の領域』も陸上の話ですね。
堂場: 箱根駅伝とドーピングをからませてしまった。主人公の検事・城戸南は鳴沢シリーズにも出ていて、かつて箱根駅伝を走った人物です。
大矢: 『独走』も異色ですね。会場からの事前質問に「スポーツ庁について考えをお聞きしたい」というのがありましたが、この小説は現実を先取りしています。
堂場: スポーツ庁が実際に生まれる前に、「スポーツ省」がある世界として、作品に登場させました。選手の強化を、国を挙げて行おうと盛り上がってきてますけど、若干疑問がある。そこまでやる必要がある?弱ければ弱くてもいいじゃない。なんで国単位なの?……そのへんの疑問を全部ぶちこんだ話です。ぜひ読んでみてください。
大矢: ここで、会場から質問をいただきました。
「取材はどうされていますか」
堂場: たとえば『ターンオーバー』で書いた「やり投」だと試合を取材しますが、原則、選手の話は聞かないようにしてます。影響を受けてそのままになっちゃうので。『チーム』の原監督は珍しいケースです。
モチーフがすべて異なる
多彩な警察小説シリーズ
大矢: 次は私のオススメに移ります。「警視庁追跡捜査係」シリーズです。「コールド・ケース」もので6巻まで出ています。犯人はわからず、捜査本部も縮小され、このままだと迷宮入り、という事件をもう一度掘り出して捜査するチームですが、堂場さんが連載で書き始めた翌年、これまた警視庁に発足しました(特命捜査対策室)。
このシリーズは主人公が二人。西川と沖田という同い年の男性なんですが、タイプが正反対。西川はインドア派、データ論理重視。沖田は現場百遍、猪突猛進型。ぱっと見仲悪いけど、実は信頼しあってる。あんたたちホントはお互い好きだよね……
堂場: そういう視点やめてください!(笑) 男同士、同期で同い年で、40歳のベテランの二人が……気持ち悪いですね。
大矢: という観点でも、楽しめます(笑)。今回は二作目『策謀』 を推します。堂場さんの警察小説シリーズはぜひ二作目を読んでほしい。一作目はキャラや設定の説明、紹介が入るから、物語の筋自体はわかりやすいのです。二作目は、ベースはわかっている前提で、純粋に事件を追う様子を堪能できます。三作目以降になると、やや捻(ひね)ってきませんか?飽きっぽいんですか?
堂場: 読者が飽きるんじゃないかな、と。
大矢: 『策謀』は5年前の放火事件を追いますが、捜査の途中、刑事がお昼ご飯何食べるとか、喫煙場所がなくて探す等、嗜好品や食事や街の描写がいっぱい出てくることで、刑事の人となりがわかるんですね。
堂場: 喋りではなく、登場人物の持ち物や行動で性格を表したいと思っている。それは常に心がけています。
大矢: 堂場さんの警察小説シリーズは、全部モチーフが違いますね。鳴沢了はハードボイルド的、高城賢吾は行方不明人捜しの部署、「アナザーフェイス」は家族もの。
堂場: 主人公がひとりで子育てしてる。
大矢: 奥さんを亡くし、小学生の息子と二人暮らしになった刑事が総務的な部署に異動しているんですが、能力を買われて、ちょこちょこ捜査へ協力を頼まれる。
堂場: モチーフとして重要なのは子育ての方なので、プロットは、意外とスッキリはっきりくっきりしています。かたや、『逸脱』の澤村慶司は、私の作品中、最も上滑りしてるキャラクターですね。気合いだけ入ってうまくいかない。
大矢: 一之瀬シリーズは、新人刑事ですね。
堂場: 自分と同年齢の人物だと現役感が薄れてきます。それで思い切って、すごく若い20代の警察官を主人公にしました。リアルタイムにリンクし、作中で一歳ずつ年をとり、最終的に2010年代の東京と一之瀬を描こうと企んでます。
大矢: 一番新しいシリーズは「犯罪被害者支援課」。事故や事件の被害者遺族のケアをする部署。捜査じゃないんですね。
堂場: 実際に警視庁にあるのは「支援室」で、それを拡大し、より大きな形にして書いてみました。
大矢: ほかのシリーズに比べると、女性が活躍しています。
堂場: 被害者や被害者の家族は、女性が多いんです。とくに性犯罪被害がすごく多い。女性が寄り添って支援する方向にもっていかないと、リアルにあわないんです。
大矢: 刊行されたばかりの二作目『邪心』は、リベンジポルノの話ですね。
堂場: 流行(はや)りものにはすぐ食いつきます。
大矢: それでは、ここで再び、事前にもらっていた会場からの質問に答えていただきましょう。
「書く上での苦労はありますか」
堂場: 何を書いてもあまり苦労はないんですけど(会場どよめく)、感じないだけかな。リアルな事件をヒントにするので、ネタ元は新聞とテレビのニュースです。でも、実際の事件がモデルにならないよう、虚と実の駆け引き、バランスのとり方が一番面倒くさいです。
大矢: 「新しいシリーズが生まれるときは事件と登場人物、どちらが先ですか」
堂場: シリーズによります。アナザーフェイスだと大友鉄という人間が先、追跡捜査係はストーリーでした。これ、最初は雑誌連載だったんですよ。毎月交互に語り口、視点人物を替えることにしよう、と。すると自然にバディものになったんです。
大矢: 「鳴沢シリーズや高城シリーズのタイトルは、どうしてディック・フランシスの競馬シリーズの邦題のように二文字なのですか」
堂場: ぶっちゃけていいですか? タイトルが大きくなるから! これは大事でしょう。最初の『雪虫』は意図なく二文字だったんですけど、タイトル目立つね、ってことになり。造語もあるから、変換して出てこない言葉もありますけど、ずっと続いてます。
連続殺人犯を描いた
かつてないジャンルの作品
大矢: いよいよ、堂場さんのセレクトです。二作ご用意いただきました。まず、「堂場瞬一を作った、堂場さんが影響を受けた一冊」をお願いします。
堂場: 小説じゃないです。『ザ・コールデスト・ウインター 朝鮮戦争』。著者はデイヴィッド・ハルバースタム。本書は彼の絶筆です。仕上げた直後に交通事故で亡くなってしまいました。
大矢: 朝鮮戦争について、関係者に聞いた話ですね。
堂場: アメリカ人が書いた朝鮮戦争のバックグラウンド ――要は全篇マッカーサーの悪口ですが、なにしろ物凄い数の取材をしています。上・下巻で200~300人くらい。そのエネルギーはすごいです。ハルバースタムの場合、政治的な作品だけでなく、スポーツも書いています。両方をやる人、日本にいないんです。スポーツも戦争モノも書く、珍しいジャーナリストですね。
大矢: それを小説でやっているのが、堂場さんですよね! ハルバースタムの『さらばヤンキース』『男たちの大リーグ』なども新刊では入手不可ですけど、すごく興奮して、いい映画をみているような本です。機会があればぜひ。
そして次はお待ちかね、堂場さんが選ぶこの一冊。最新刊『Killers』 、一〇〇冊目の著書です!
冒頭で、ある老人の他殺体が発見されます。身元がわからない。これ誰なんだ……という現代から、舞台は昭和30年代に飛びます。当時、ある使命感を持った連続殺人鬼が渋谷に現れる。その殺人者側の視点で、殺人者の思いや血脈のようなものが描かれます。50年経っても捕まらない殺人者を、ずっと追い続ける警察との戦いの話で、読み出したら止まらないんですが……
堂場: 最初は、連続殺人を書こうとしたわけじゃないんです。私の仕事場がある渋谷という街は、永遠に工事が終わらない。今は2020年の東京五輪に向けて工事を続けているけど、50年前も同様に、オリンピックのためお化粧直しをした。この街は随分変わるんだね、という話から気楽に、1500枚くらいで、50年間の変遷を追う、渋谷の街小説を書くつもりでした。それがいつしか、当初の意図が引っ込んで、50年人を殺し続ける奴の話に……
大矢: 殺人現場となる背景の街の様子が、昭和30年代、40年代、バブル期、と時代ごと、随所随所に描かれて、風俗小説としても読めますね。
堂場: 本当なら、1970年代の、パルコが出来て渋谷が若者の街になってきたことを書いておくべきだったのですが、そこは飛ばしました。……いや、困ったな。自分で選んでおきながら、この小説については、なんか喋りにくいの。
大矢: 街小説としての側面で見ると、昭和30~40年代の猥雑(わいざつ)な感じ、一本路地に入ると戦前からの木造の建物がひしめきあっていた、同じ場所に10年後には綺麗なカフェができている……そういう変化は、渋谷の街を知らなくても、日本人なら体感できます。
けれど、主人公が人を殺したい理由、本作では、連続殺人犯に憧れて自分も人を殺すようになる人物も出てくるんですが、なぜ人を殺すのかという動機が最後まではっきりせず、わかりやすい答えが出ないから、読後にもやもやが残るんでしょうね。
堂場: サイコ系の犯人でもなにがしかの動機はある、ということで書かれた作品は多いですが、今回は、理由もなく、息をしたり水を飲むのと同じように人を殺す。そういう犯人です。……まるで、でっかい穴を掘って自分が覗き込んでるような感じ。何やっちゃったんだろ、俺。すごい不安なの。
大矢: 構成自体はエンターテインメントになっていますよね。最後の一章は、警察が犯人に追いつくか逃げられるかドキドキで、そこでそうくるかという展開はかなりエキサイティングです。
堂場: 小説の技術としては考えていたんでしょうが、なんか違うの。「降りてきた」感じ。自動筆記のような……。なので、この作品について聞かれてもうまく答えられないんです。
大矢: 書かされた一冊、って感じですか。
堂場: 書き上げたあとの記憶がしばらくなくて、はっと気がつくと原宿にいたんです。おなか減ったなと思って、時計みたら3時間経ってたので、しょうがないから鯖味噌定食食べて帰りました。
大矢: 従来の堂場作品で、本書とモチーフとして近い要素があるな、と私が考えたものを紹介します。『Sの継承』『解』『歪(ひずみ)』の三作です。
堂場: 『Sの継承』は、50年前のあるテロの手法を現代に甦らせて、またテロを起こそうとする話。50年前の犯人と現在のテロ犯の間には断絶があり、直接のつながりはありません。それをつなげてみようとしたのが今回かな。モチーフとしては近い。でもこの話はエンタメですよ。そんなにテーマ性が強いものではない。
大矢: 時代を追って、順に書いていったという点では『解』。
堂場: 「平成」を振り返ってみようと書いたのがこれ。バブル絶頂期から東日本大震災までの歩みを、時代を追って書いてみました。そして最後に物語が崩壊する、という小説ですね。
大矢: 『歪』は澤村シリーズの二作目ですけど、半分くらい犯人側の視点で書かれています。初めての犯罪者視点の作品ですね。
堂場: これは、比較的理解できます。目的はお金、コスパだよね、という犯人です。
大矢: 手法としての集大成ともいえる『Killers』。だけど、テーマは違うものが乗ったぞ、ということですか。
堂場: 「正義」と「悪」じゃないんですね。主人公は人を殺すのが「悪」だという意識がない。彼にとってはそれが正義、それが普通のこと。倫理観がそもそも違う世界なんじゃないかな。
大矢: 追いかける警察の側は、後手後手にまわって。
堂場: たとえ捕まっても、大団円とはならないと思うんです。
大矢: 若者が連続殺人犯に憧れて弟子入りしますけど、その弟子たちは、師匠ほど突き抜けてないですね。
堂場: 彼らは悪事を犯すことに快感を抱いていますが、主人公はそれを否定している。むしろ「使命」だと言っています。
大矢: 読者には、本書のどこを読んでほしいですか? あるいはこの場面に苦労したというのはありますか?
堂場: 普段はいろいろ考えるんですよ。伏線ここに張って、回収して……と。でも今回はほんと、全然覚えてないんです。
大矢: 一種、特別な一作ではありますね。
堂場: 特殊ですね。理解は難しいかもしれない。
大矢: 堂場さんの警察小説、犯罪小説は基本、読者を共感させるものではありませんよね。
堂場: 好きじゃないんですよ。僕が読むときは、共感できない人間を読みたいんです。そういう読書をしたいから、自分でもそういう話を書く。
大矢: 感情移入する隙はあるのか、ないのか……かつてないジャンルの小説です。これから読まれる方はどうぞお楽しみに!
このあとは、質疑応答に移りましょう。(以下、質問はQと表示)
Q: 「物語を書きたいと思われたきっかけはなんですか」
堂場: 小さい頃からたくさん本を読んできて、自分でも書けるんじゃないかと勘違いして今に至ります。
大矢: いえいえ、ぜんぜん勘違いじゃなかったですねー。では、次の方です。
Q: 「デビュー後、作家として確立されるまでに、モチベーションとなったことはなんですか」
大矢: 堂場さん、長い間兼業でしたよね。それってたいへんじゃなかったですか。
堂場: その切り分けはできていたのですけどね。結局は「書きたりない!」という気持ち。これが常に、書くことへのモチベーションになっています。作家としては確立しておりません。ぜんぜん満足してない。
大矢: じゃあ、次は200冊を突破されたとき、どこまで達成できたか、うかがいましょう。
堂場: ぜったい「まだまだ」と言うでしょうね。
Q: 「作品のモチーフを選ぶのは、どんなきっかけからですか」
堂場: ナマのニュースに感化されますね。新聞記者時代の経験に基づく「読み方」から、世の中は今、こういう趨勢なのか、というのが見えてきます。それがベースになってますね。
Q: 「名古屋を舞台にするならどんな小説が書けそうですか」
堂場: 相当難しそうです。昨日からいろんな方と話をしてますけど、人間関係がべったりしている土地柄のようなので、すぐに犯人がわかっちゃいそう。書くとしたら……転勤族の異邦人がここにきて、すっごい苦労するとか(笑)
Q: 「これから新たに書いてみたい競技はありますか」
堂場: サッカーとバスケ、卓球以外、ですね。スポーツは迫力ある試合のシーンを書きたいのですが、これらの競技は試合展開が早すぎて絶対書けないと思います。たとえば卓球だと、10秒の間に何回ラリーできるか……いろいろ考えちゃうと、書ける気がしないのです。
大矢: 先ほども話にでた『20』 はプロ初登板初先発のピッチャーがノーヒットノーランをやるお話ですが、その最後の1イニングだけ、20球の話じゃないですか。20球で一冊書けるのに……
堂場: スミマセンでした(笑) 今まで書いてない競技で、なにかよいテーマがあれば……とチャンスは狙ってます。
(会場の方から)「テニスはどうですか」
堂場: うーん、難しいですね。野球は投球の間があるから、書きやすいんですよ。ピッチャーも守備陣もバッターもその間にいろいろ考えていて、その様子を書けるので。
Q: 「映像化されたドラマをご覧になって、え、そういう解釈? とか、こうきたか! 等々思われたことはありますか」
堂場: 尺の関係でストーリーが変わることはありますが、キャラクターは、まあそうかな、って感じです。
大矢: 鳴沢了は坂口憲二さん、大友鉄は中村トオルさん、高城賢吾は沢村一樹さん、澤村慶司は反町隆史さん、今度放映される「誤断」の主演が玉山鉄二さん、ですね。
堂場: だいたいイメージ通りです(笑)。イケメン俳優さんにやってもらえてよかったです。
Q: 「幼少期に読んで心に残っている本はありますか」
堂場: 自分で意識して初めて文庫を買うようになったのは、小学生高学年の頃、SFのペリーローダンシリーズをよく読んでいました。でも、まったく影響は受けてないですね。影響されたのは、高校生以降です。ここでハードボイルドに手を出すわけです。結構ひねくれてる高校生ですね。
日本の作家は読んでいません。自分の知らないこと、知らない国の話を知りたいから、海外作品を読みます。それは昔から変わらないし、今号も変わらないでしょうね。最近読んだ本では、『ゲルマニア』が、設定が面白かった。ドイツのナチス時代のミステリーです。
Q: 「具体的にこの翻訳物の影響を受けている、というのは、ありますか」
堂場: 失踪課は、もろロス・マク(ドナルド)、リュウ・アーチャーです。すごく意識していますね。
Q: 「プロットをたてて書きますか」
堂場: 出来上がって書き直しになるのは、ぜったいやりたくないですから、最初にあらすじをちゃんと作って、編集担当と入念に話をします。
Q: 「初心者にもお勧めの堂場作品を教えてください」
堂場: 警察小説なら、間口が広いという意味で「アナザーフェイス」シリーズかな。ハードでもないし、キャラクターに感情移入もできるでしょうから。スポーツ小説なら、『チーム』『大延長』。より間口が広いのは『大延長』 でしょうか。私にしては珍しい爽やかな高校野球の小説です。もしかしたら黒歴史かも…?(笑) 野球は永遠に続く、という前向きなテーマです。
大矢: まだまだお話は尽きませんが、時間となりました。最後に堂場さんにご挨拶をいただきましょう。
堂場: 今回の名古屋のように、52歳になっても訪ねたことがないところに初めて行ける、作家というのはいい商売だなと思っています。またどこかでお会いしましょう!
(2015年10月17日 名古屋市の国際デザインセンターにて開催)
※本記事は月刊ジェイ・ノベル2015年12月号掲載記事にウェブ限定の内容を加えて再編集したものです。

どうば・しゅんいち
1963年生まれ。青山学院大学国際政治経済学部卒業。新聞社勤務のかたわら小説の執筆をはじめ、2000年『8年』で第13回小説すばる新人賞を受賞し、デビュー。警察小説とスポーツ小説の両ジャンルを軸に、意欲的に多数の作品を発表している。2015年10月に著書が通算100冊に到達した。

おおや・ひろこ
書評家・文芸評論家。名古屋市在住。新聞・雑誌への書評寄稿の他、ブックナビゲーターとしてのラジオ出演や読書会主宰、イベント司会など名古屋を中心に活躍。著書に『脳天気にもホドがある。』(東洋経済新報社)、『読み出したら止まらない! 女子ミステリー マストリード100』(日経文芸文庫)など。『文藝別冊 堂場瞬一』(河出書房新社)ではスポーツ小説の紹介を担当。