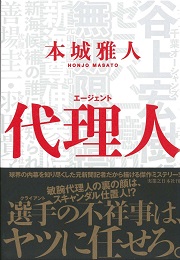11月の文芸書新刊 本城雅人『代理人(エージェント)』刊行記念
スポーツの裏に潜む、胸震える「隠れたドラマ」を描く

2017年春、『ミッドナイトジャーナル』で吉川英治文学新人賞を受賞するなど、いまもっとも脂の乗った作家のひとり、本城雅人さん。本城さんがこのほど小社から上梓した『代理人(エージェント)』創作の背景や、作品にこめた思いについて、伺いました。
構成/宮田文久
――『代理人』は、金に目がないといわれ「ゼニバ」と揶揄されるスポーツ代理人・善場圭一が、契約する野球選手たちが巻き込まれていく事件を解決していく連作ミステリーです。野球ファンも、野球に興味がない人も、共に楽しめる作品になっていますね。
本城:代理人という存在は、選手と個別契約をしている弁護人のようでありながら、同時に世話人のような存在です。ひとりの選手が複数の事件に巻き込まれていくということはなかなか考えづらいですが、代理人であれば、いろんな選手がそれぞれ事件に遭遇してしまう度にその解決に向かう――そうしたミステリーの形がとれると思ったんですね。
そもそも日本では、まだ代理人をめぐるマーケットがそこまで成熟していません。一方でアメリカでは、ハーラン・コーベンという作家が代理人を主人公にしたミステリーを描いており、人気シリーズになっています。野球そのものにだけでなく、もっと広くライトな興味を持っている、たとえば最近の“カープ女子”のような人たちにまで届く作品になればいいなと考えながら書いていきました。
――かつて産経新聞・サンケイスポーツで野球記者としての取材・執筆を重ねてこられた本城さんは、以前に本作の登場人物たちが登場する長編はひとつ手がけられていましたが、今回は、暴行、女性問題、違法賭博など、選手たちがかかわってしまう様々な“事件”があり、善場が問題解決に奔走する、という構造の作品にされています。そのバラエティ感が読みどころのひとつですね。
本城:僕は2009年に松本清張賞最終候補まで残ることができ、デビューとなりました。その頃までは「プロ野球選手になって活躍している人間が、人生を棒に振るようなことをするだろうか」といったような考えが一般的だったんですが、その後、暴行にいじめ、違法賭博に覚せい剤と、さまざまな事件が表沙汰になっていきましたよね。
――先日も不祥事件を起こした投手が処分されたばかりですね。一方で、大物スラッガーや、メジャーでも活躍したベテラン投手が戦力外通告を言い渡されたことも話題になりました。事件を擁護するわけではなく、選手が非常にシビアな環境のなか、誰もが抱える人間としての“弱さ”と戦っていることが、改めてよくわかります。だからこそ善場も、契約選手の全打席・全投球をチェックして全身全霊で球団と交渉し、有利な条件を勝ち取ろうとします。
本城:選手たちは何億円もらおうが、常に不安や孤独と戦っているんだと思います。だから、ドラッグに頼ってしまう人間もいるし、酒におぼれて暴力沙汰を起こしてしまう人間もいるのでしょう。その仕組みというのは一般社会と何も変わらないんですよね。何も“敗者”だけが犯罪をおかしているわけじゃなく、一見華々しい“勝者”に見える人でも同じなんです。そうした紙一重のところで戦っている選手たちは、きっと同じように「人生を賭けている」代理人でないと、自分の身を預けたくはないだろうな、と。
――度重なる肘の手術を共に戦ってきたピッチャーと善場が、緊迫感のある会話を繰り広げる場面など、魅力的なシーンがいくつもありますね。
本城:他方で、選手が事件に巻き込まれたとき、選手だけを守ろうとするのではない、というのが善場の態度です。選手だけを守ろうとしたら、本当は有罪なのに無罪だと言い張る弁護士のようなことになってしまう。しかし、彼は選手を「球界の財産」として考えるからこそ、本当にクリーンなのかどうか見極めるわけです。
――自分の目を見て話してくれ、隠し事をするな、と善場は口を酸っぱくしていいますね。そんな彼は「メジャーで鉄人と呼ばれた選手の代理人を長く務めた弁護士」――ドーピング問題が発覚した際に真っ先に検査を主張した人物を目標にしている、という会話があります。選手は「リーグとファン、そして代理人の三者共有の財産」だというのがその人物の理論ですね。
本城:これは、連続試合出場の世界記録をもつ「鉄人」リプケンの代理人をしていた人物のことですね。僕は90年代から、野茂英雄さんや吉井理人さんをよく取材していたので、メジャーの代理人というあり方にはずっと興味を持っていたのですが、2000年から2001年、新聞記者時代に留学した際に集中的に学んだんです。ニューヨーク大学で代理人が講師を務めている授業があり、毎回現役のエージェントを呼ぶというものでした。
日本に戻ってからも、スコット・ボラス(編註:多くの高額契約を結んできたMLB代理人の第一人者)やアーン・テレム(編註:過去に松井秀喜やダルビッシュ有を担当)に取材しながら「球界未来図」という新聞連載を担当するなど、継続的に勉強してきたんです。まだほとんど情報がないころでしたが、必死に英語の資料も漁りましたし、ボラス日本事務所の代理人とはその頃からの仲ですね。今作の執筆にも、そうした積み重ねが活きています。
――なるほど。善場の姿というのは、そうした取材や学びの蓄積の結果できあがっていったものなのですね。それにしても、選手という「共有財産」をめぐって、徹底してロジカルに思考して行動しながら、ギリギリまで選手との信頼関係を探ろうとする情も持っている善場は、面白い人物像ですよね。
本城:僕が考えたのは、選手と“対等”である、というあり方でした。偉そうにもしないし、逆に荷物持ちにもならない。超一流の選手にも、若手の選手であっても、同じようにきちんと丁寧語で喋る。その“対等”である態度が絶対に大事だろうな、と。
ただただ「優しいだけ」の代理人というのは、選手にとってどうなのかな、という思いがあるんです。単に優しい、守ってくれる代理人というのは、僕が描きたい代理人の姿ではありませんでしたし、そうではない“対等”な人物がいたら、選手をめぐる問題はもっとなくなるだろうと感じているんですね。
――現実の野球界では、なかなかそうした対等な人物、場合によっては孤独な心境さえも打ち明けられる人物が、選手のまわりに少ないのかもしれませんね。
本城:そうだと思います。以前でしたら、記者という存在がそうでした。毎日顔を突き合わせ、自主トレも帯同し、ドラフトから移籍まで陰日向に面倒を見ることさえある――それはすべて記者が第一報を書くんだという“対等”な関係のうえで成り立っていることだった。しかし、メディアは以前よりも力を失っていますし、本作に出てくる羽田貴子のようなマネジメント会社も間に入ってくるようになりましたから、関係性は変わってきていますよね。そして先述したように、日本の代理人のマーケットも、まだそこまで成熟していない。
――だからこそ、この作品で描かれる善場のあり方が、とても先鋭的で、新鮮なものに映ります。ピッチングやバッティングのわずかな変調も見逃さず、その発見が事件の解決に繋がっていくストーリーは非常にスリリングですし、“対等”だからこそ、場合によっては選手に対して非常に厳しい判断もくだしますよね。
本城:執筆していたときに考えていたのは、「答えをひとつにしたくない」ということでした。善場は、事件の真相に行き当たったとき、自分のなかの基準と照らし合わせながら、世間の白黒のつけ方とは異なる、非常に“複合的”な判断をすることがあります。悪は悪で断じるのですが、正義をめぐる答えはひとつではないんですね。
今の世の中は、たいてい答えがひとつですよね。野球にかんしても活躍したら絶賛して、WBCで負けたり事件を起こしたりしたら非難する。野球の外に目を開いても、不倫報道はひどいですよね。当事者が社会から攻撃され、打ちのめされてしまう。
――それだけの覚悟があるのなら、好きになった者同士の思いを断ち切るなんてことは誰にもできない、と作中でも登場人物が語りますね。
本城:そうした、答えがひとつになりがちな世の中にこそ、善場の複合的な回答は有効だと思うんです。何かやらかしてしまったらもうダメ、一回の過ちをおかしただけでも再起できない、チャンスをくれない現状とは、異なる対応はとれると思うんですよね。何も僕は、社会派ミステリーとして野球界にメスを入れる、といった気持ちで書いているのではないんです。冷血に見えるけど実は彼女もいて、助手の元カメラマンや、腐れ縁の仲がいい新聞記者も周りにおり、マネジメント会社社長の羽田ともしょっちゅう顔を突き合わせている……というような、決して“スーパーマン”ではない人間くさい善場の姿を通して、“遠い世界”ではない出来事に触れてみてほしいんですね。僕らがスポーツに感動するのは、そこに現れない「隠れたドラマ」を肌で感じるからだと思います。そして僕は、第一線で活躍するアスリートというのとは異なるテーマでスポーツ小説を描くことで、そうした僕たちの日常と地続きな「隠れたドラマ」を描きたいと思っているんです。
――冒頭で“カープ女子”の話が出ましたが、やはりそうした意味で、野球ファンでもなくても楽しめる小説になっていますよね。
本城:野球ファンのお父さんが楽しそうに家のリビングで読んでいて、別に野球が好きでないお母さんや娘、息子が「何読んでるの?」といったら、「面白いよ」といって回し読みしてくれる--そんな作品になっていたら嬉しいですね(笑)。その先に、スポーツ小説やスポーツミステリー、そして代理人というあり方が日本社会に根づいていく未来があるのでは、と考えています。
(2017年11月 都内にて)

ほんじょう・まさと
1965年神奈川県生まれ。産経新聞社入社後、産経新聞浦和支局を経て、サンケイスポーツで記者として活躍。プロ野球、競馬、メジャーリーグ取材などに携わる。退職後、2009年に『ノーバディノウズ』が第16回松本清張賞候補となり、デビュー。同作で「第1回サムライジャパン野球文学賞」大賞を受賞。16年『トリダシ』が第18回大藪春彦賞候補、第37回吉川英治文学新人賞候補となる。17年『ミッドナイト・ジャーナル』で第38回吉川英治文学新人賞に輝く。他の著書に『球界消滅』『スカウト・デイズ』『嗤うエース』『英雄の条件』『紙の城』『監督の問題』など。