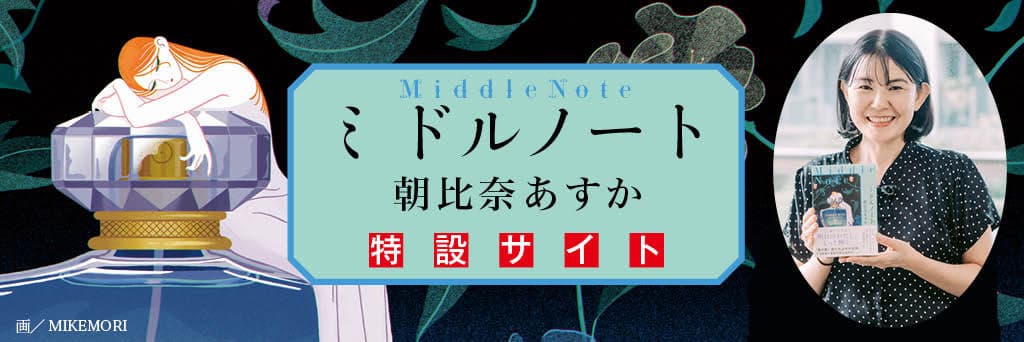
朝比奈あすか 最新刊『ミドルノート』――明日のあなたが、もっと輝けますように。すべての女性にエールを贈る、注目作家の意欲作!
『ミドルノート』購入はこちらへ
→https://www.j-n.co.jp/books/?goods_code=978-4-408-53843-3
★刊行記念特別対談 桜木紫乃×朝比奈あすか

シクシクしやすい時代を生きる。あなたも わたしも(前編)
朝比奈あすかさんは、長編小説『ミドルノート』(実業之日本社)、桜木紫乃さんは、写真絵本『彼女たち』(KADOKAWA)。自分の「いま」に悩み、もどかしさを抱える女性たちを描いた作品を、このほど同時期に上梓されたお二人。書店での偶然の出会いから数年経ったこの秋、待望の初顔合わせが実現! 創作背景やデビュー前のエピソードなど、存分に語りあっていただいた対談の模様を〈前編〉〈後編〉にわけてお届けします。
写真/中川正子 構成・文/Webジェイ・ノベル編集部
◆“シクシク”悩み、“シクシク”生きる30代
――お⼆⼈は、仕事では初顔合わせですが、以前⼀度、お会いになったことがあるそうですね。朝⽐奈:数年前、⽇⽐⾕の書店を訪ねた時、ちょうど来店されていた桜⽊さんを書店員さんがご紹介くださって、ご挨拶したことがあるんです。今⽇は、再会できて光栄です!
桜⽊:こちらこそ、よろしくお願いします。
『ミドルノート』興味深く拝読しました。登場人物たちは「ゆとり世代」になるのですよね。実は我が家に、ガチで“ゆとりくん”がいるんですよ。
朝⽐奈:そうか、あの時に話しておられた息子さんが――
桜⽊:今年31歳。『ミドルノート』に出てくる西くんみたいなタイプ。まさに、うちにいるの(笑)
朝⽐奈:前回は、ほんの短い会話を交わしただけでしたけど、「息子がマイペースすぎて」って私が言ったら、「一緒! うちもマイペースなのよ」と言ってくださったのがすごく嬉しくて、よく覚えています。息子は人の目を全然気にしないし、自分が楽しければそれでいい、友達が多くなきゃとか、そういうのもありません。当時は中学生だったので、ちょっと心配だったんですけど、最近は逆に、羨ましいなと思っています。
桜⽊:うちの“西くん”も、お給料で趣味のガンプラを買って、綺麗に作った写真をアップしたりしてますよ。すごく楽しそう。
朝⽐奈:わあ。めっちゃいいですね。
桜⽊:実は最近、『ミドルノート』も含め、30〜40代の書き手の作品を続けて読む機会があって、ちょっと衝撃を受けたんです。登場⼈物がみんな、シクシク悩んでるのね。誰かと比較してはシクシク、自分って何だろうとシクシク、立ち位置も居場所もわからない――たまたまかもしれないけれど、『ミドルノート』も含め、そんな作品が続いたんですよ。
私の担当美容師さんがまさに30代半ばの方で、「立て続けにそんな内容でさ」って話してみたの。すると彼女があっさり、「私たちはバブルの時代も、日本が上り調子だったことも知らない。物心ついた時には生活は楽じゃなくて、親はやりくりに困ってることが多かったです。日本が他国に追い抜かされて、差がついてきた、そういう時代を反映してるんじゃないですか」と返ってきて。小説は時代を映すものだけど、やっぱりそうなのかって、びっくりしました。
朝比奈さんが今回、人生のミドルノート、30代という年代を選んだのは、どういうきっかけからですか。
朝⽐奈:この小説は「日経xwoman DUAL」という、共働き子育て世代がターゲットのWebメディアで連載したもので、担当編集者も30代前半の女性でした。それで、私よりひとまわり以上若い今の30代はどういう状況で、何を感じているのかと興味が湧き、「会社の同期」という設定で物語を作ることにしました。
30歳って、その先の人生が分岐する始まりの時期だと思うんです。独身の方、既婚の方、子どもがいる方、いない方、働く場合も正規雇用か非正規雇用かなど、立場はそれぞれです。この世代には、⾃分が何を求めているのか分からなかったり、選んだ道に自信が持てず、この⾯で私負けてる、ここは勝ってるとか、常に他⼈と⽐較してる⼈が多いことに、書き進めながら改めて気づきました。
桜⽊:こんな日常だと、疲れてしょうがないだろうな、って思えるぐらいシクシクしてますよね。これって、この世代特有で抱えている問題なのかな。

◆「生きづらい」という言葉
朝⽐奈: 今の30代は、SNSを通じて他の人の生活の良いところだけついばむように見えちゃうこともあったりで、私たちの頃よりもっと、シクシクしやすい時代を生きなくてはなりません。だからこそ、そうやってもがく中で、誰とも比較できない自分の真実を見つける話にしたいと考えました。桜⽊:私は若い頃、やはり30歳くらいの時かな、物の見方や興味ある話題が、いわゆるママ友、保育園や幼稚園のお母さんたちとやけに合わないって、気付いたの。ところが、私が合わないと思う以上に向こうも感じていたみたいで、だんだんうまくいかなくなっていったんです。一緒に何かをするとか、子供のために仲良くしなきゃとか、そういう場面で、途端につらくなる。
今の30代のつらさはあれに近いのかしら。あの違和感が、モラハラとか、パワハラなどの形をとって、職場や友人や夫婦間でも起きているとしたら、そりゃつらいだろうなと思います。
ただ、そこに「生きづらい世の中だから」って言葉を与えて納得させがちなことについては、疑問に感じますね。「生きづらい」という言葉。朝比奈さんはどう思いますか?
朝⽐奈:流行ってますよね。昔はそんなふうに言いづらかったはずなのに、皆がライトな感じで、いとも簡単に言えるようになって。「病んでる」も良く聞きますよね。
桜⽊:本当に病んでる人は、相手に向かって病んでるって言わないよね。
朝⽐奈:自分が生きづらいことに気づいてない人こそが、本当の生きづらさを抱えているのでしょうに。ただ、そうやって口にすることでつらさが薄まって、気持ちを楽にできるのかしら、と思うことはあります。
桜⽊:私は自分から生きづらいって言ったことないんだよね。安易に使うのを控えたいと思っている年代かも。流行ってるから、みんなその一言で片付けようとするんだけど。どう駄目なのか、どうすればいいのか、自分の言葉を得られたらいいのにね。

◆50代でできた友達がきっかけで……
――朝比奈さんは、『彼女たち』をどのように読まれましたか。朝⽐奈:出口が見えにくい日常の中でも、三人の彼女がそれぞれ自分を見つめ直し、よりどころを探っていく姿が、とてもいいなと思いました。
桜⽊:私は今50代後半だけど、50代って、過ぎてきた30代、40代をどう生きてきたかが出る10年間だと思うんです。30代が人生の基礎で、40代に応用をきかせてきたものが、50代でどれだけ形になるか。若い頃は友達っていなかったけれど、最近になって「友達」と呼びたい人と出会うようになったんです。
朝⽐奈:仕事とは関係ない方ですか。
桜⽊:まったくの異業種。その彼⼥との出会いで、『彼⼥たち』が⽣まれたんです。⼀話⽬の「イチコさん」のモデルが、50代になってからできた友達。今59歳で、実際に大学の教授なんですよ。
朝⽐奈:えっ、そうなんですね!
桜⽊:若い頃の“やけに合わない関係”とは逆で、最近、相手のことを「この人、ユニークだな、なんかおもしろいな」と思ったら、向こうも「サクラギってちょっとおかしいな」と思ってくれるようで、でもそれがいい具合なんですね。よく動く免震構造というか、いいゴムだから揺れても大丈夫。友情関係は動じない。
朝⽐奈:最初は、お互いをおかしいと思わないわけですよね。常識的な出会いで、話して、お互いを掘り下げていくうちに、おかしかったってことに気づいていく感じなんですね(笑)。
桜⽊:ちなみに担当編集者はみんな、私にとっては“戦友”。あるいは、作品を作り上げる“共犯者”でもあったり。そんなふうに捉えています。けれど、よく考えたら、私の周りにいる編集者たちも私を「ちょっとおかしい」と思ってるってこと?(爆笑)

桜⽊: 『彼女たち』の裏話を、少ししますね。担当編集者から「絵本を作りませんか」という誘いをもらって相談するうちに、「絵」ではなく「写真」と文章を組み合わせようということになったの。写真ならぜひ中川さんにお願いしたくて、散文詩のような文章一冊分を見ていただいたんです。「お引き受けします」って返事をもらって、「やったー!」と思ったら、中川さんから注文が来たのね。「せっかく小説家が書かれるのだから、ストーリー性のあるものにした方がいいんじゃないですか」って。それで、新たに書き下ろしたものを読んでもらって、写真を撮っていただいて、今のような構成に落ち着いたんです。
中川:(対談撮影中の中川さん、飛び入り)
そこはちょっと訂正があって。“小説家だから”じゃなくて、“せっかく桜木紫乃さんなんだから”って私は言いました。桜木紫乃さんの物語を、私が読者としてぜひ読みたいです! と編集者経由でお伝えしたんです。
桜⽊:ほら、中川さんも編集者も、めっちゃ“共犯”だ!
朝⽐奈:でも、そうやって、ストーリー仕立てで書いていただいて、本当によかったです。『彼女たち』に収められているのは短い文章なのに、桜木節、というのでしょうか、桜木紫乃さんならではの「この表現!」みたいなものが随所にあって、堪能できます。
桜⽊:「桜木節」って、どういうの?
朝⽐奈:体言止めではないんだけど、「独特の文章で言い切る」感じ、かな。例えば、わかりやすい例だとーー「なにも片付けられない毎日に、やり残した家事が散らばっている」にハッとしました。新鮮でシンプルな表現なのに、部屋の様子がすごく伝わる。「残っている」ではなく「散らばっている」と書かれるセンスかしら。
桜⽊:そうなんだ、気がつかなかった。
朝⽐奈:うまく説明できないんですけど、うーん、比喩に近いというか……動詞で比喩をする、というのでしょうか。意外な動詞が組み合わされた文体で、初めて触れる表現なのに、びしっと伝わる感じがかっこいいと思います。
桜⽊:文体ってなんだろうなあ。自分ではよくわからないんです。自分が知らない言葉は使わないようにしていますけどね。
朝⽐奈:桜木さんの文章の中でしか出会えない言葉が散りばめられ、きちっと言い切る。それが桜木節なのかもしれません。
(後編へ続く) arrow_upwardページトップへ
★刊行記念 著者エッセイ

『ミドルノート』刊行に寄せて
生まれを選べぬ私たち 朝比奈あすか
私たちは生まれを選べない。場所や親ばかりでなく、生まれる年代も選べない。『ミドルノート』を執筆しながら、そんなことを考えた。
私たちは、選べないものにより、勝手にラベリングされる。「団塊の世代」「バブル世代」……「ゆとり世代」「Z世代」など。ネットで検索したらたくさんのラベルがあった。
昭和五十一年生まれの私が、分類の仕方によって「団塊ジュニア世代」だとか、「ロスジェネ世代」などと言われているのは知っていた。ふーん、と思っていた。世代で勝手にくくられることを窮屈にも感じた。
ただ、「就職氷河期世代」という呼び名は、しっくりきていた。
というのも、私たちは、バブル時代に学生を大量採用していた企業が、バブル崩壊に伴い人件費を削減した後に、就職活動をせざるを得なかった世代だ。新卒採用をとりやめる企業も少なくなかった。私は、たくさんの企業を受けて、その多くに振られたが、友人たちもたいがい苦戦していた。新卒で非正規雇用の道を選んだり、首都圏での就職を諦めて地元に帰ったりした人もいた。
若者は権力がないから、とかく政治からも社会からも捨て置かれる。
数年前に、行政による引きこもり支援は三十九歳までだが、実際は引きこもりで最も多い年代は四十代であるという記事を読んだ。これは就職氷河期世代を、政府や企業がしっかり支えなかったことが大きな事由で、その四十代が五十代に突入し「8050問題」につながっていると思う。自己責任と厳しく扱われるのでは割が合わないくらいに、生まれ年ガチャでやられた人たちがいるのだ。
……と、こんな話をしていると、小説の内容からは遠ざかってしまうけれど、『ミドルノート』を執筆するにあたり、私が考えていたのは、生まれ年が少しずれると、見ている世界がだいぶ違ってくるということだった。
ふだんは小説を書く時に、読者層などは想定しないのだが、この『ミドルノート』という小説は日経BP社の「日経xwoman(クロスウーマン)」というWEBサイトに掲載されたもので、読者層がわりと定まっていた。
掲載当初の編集者と話し合い、私は1990年前後生まれの女性たちを主人公にしようと決めた。例の区分けによると「ゆとり世代」にあたる人たちである。(彼らもまた、大人たちの決めた教育を選びようもなく受けさせられて、勝手に「ゆとり」と名付けられている)。
「ゆとり世代」というとなんとなく若い人たちと思っていたが、いつの間にか彼らも三十代なのである。
三十歳といえば、ミドルノートの始まりだな、と私は思った。
以前、たまたまアロマ関連のワークショップに参加した時に、香水の香りは肌にのせるとトップノート→ミドルノート→ラストノートというふうに、じょじょに変化してゆくという話を聞き、面白いし、何やら暗示的でもあるなと感じていた。そして、人生の変化をこれに重ねるならば、どの世代であれ、成熟の始まりであるミドルノートは、三十歳くらいかなというのが、私の抱いた印象であった。
二十代も、それなりに大人であると当時の自分は感じていたが、思考や言動をふりかえるに、いろいろと甘いところがあった。それこそ私は、この連載をさせていただいた日経BP社には、就職氷河期のさなか新卒で採用してもらったというのに、たいした働きもせずに数年で辞めてしまった。日経xwoman連載中に、『ミドルノート』がアクセスランキングで一位を取れたと聞いて、ほんのわずかに貢献できたのではないかとほっとしたのを覚えている。
と、こんなふうに過去を振り返れるようになった今思うのは、ようやく自分が好きなことや嫌いなこと、得意分野や苦手分野がはっきりしてくるのが、三十歳くらいではなかったかということである。
とはいえ、三十歳もまだ、人生の選択の出だしのあたりにようやく立ったかなというくらいの年齢である。書いてみたいなと思い、三十歳の社会人女性の像を思い浮かべた。四人いれば、その中には一人は保活に苦しんでいるママがいるだろうし、一人は専業主婦の道を選ぶ人もいるだろうと、私は考えた。
「主人公は、バリキャリ、保育園探しに奔走する女性、寿退社する女性、といった感じになりますね」
そう告げると、私よりひとまわり若い編集者が、
「うーん。保活に苦しむことや寿退社は、かなりレアケースかもです。今は保育園が、わりと預けやすくなっているんで。少子化ですし、自治体も色々と工夫をしているようです」
と、指摘してくれた。
「え、そうなのですか」
「今は、夫婦で働くのが当たり前って感じで、よっぽどの事情がないと出産、ましてや結婚で、会社を辞めたりはしないです。私の周りも皆、共働きです」
三十代の編集者がそう言うのを聞いて、びっくりしたし、羨ましくも感じた。
その後、編集者は実際のデータを調べてくれたり、それに関する新聞記事などの資料を送ってくれた。実際に、待機児童の数は大きく減っているそうである。
世の中は、知らぬまに良い方向に行っているのだな……
感心した私が、別の場でその話をしたところ、
「いや、働きやすくなったというより、専業主婦になれる人が少なくなっただけでは? そのせいで子供が減って、保育園に入りやすくなっただけでは?」
という指摘もされた。
実際のところ、日本は諸外国の発展に比べ、足踏み状態が続いている。相対的に見れば、貧しくなっているということだろう。賃金は上がらず、子どもを育てるためにパートや派遣といった非正規の形態で働かざるを得ない女性も多い。それでいて、男女の役割分担に関する古い社会通念が蔓延(はびこ)っている日本(2023年のジェンダーギャップ指数で日本は146か国中125位!)では、子育ても家事もまだまだ男性とイーブンには分け合えていないから、「女性が輝く社会」どころか、女性が疲弊する社会になっているという実感は、SNSの声などを聞いていても感じられる。
自分たちが割をくった世代だと思っていたが、国際競争力の落ちた今の日本で生きるゆとり世代の方々も、就職氷河期世代とは違った種類の苦しみや閉塞感を抱えているのかもしれない。
それにしても、ひとまわり年下くらいなら、担当編集者に数人いるし、他にも趣味を通じて知り合った若い友人たちはいて、ふだんは年齢差を感じていなかった(向こうが合わせてくれているのかもしれないが)。
しかし私は改めて、彼女たちに仕事に対する意識や、子育てで感じていることなどを聞く必要があると感じた。十年ひと昔とはよく言ったもので、生まれが十年違うだけで、生きてきた空気がだいぶ違うのだ。
話を聞くとやはり三十代には三十代の、四十代には四十代のものの見方があるし、そこには時代性も大きく影響を及ぼしている。そのことを面白いと思ったし、自分にどんぴしゃりの年代の主人公を描くことに比べて、世代間の差を味わったり、そこに注目したりして、楽しみながら描くことができた。
加えて、執筆期間はコロナ禍とも重なった。あの時期に何歳だったか、どういう立場だったかという観点でも、世代の差はあると思う。
とかく「〜世代」とくくられて単純化されることに抵抗を感じたこともあったが、同級⽣や同期としか共有できない感覚があるのも確かだ。と、同時に、世代を超えて分かり合える普遍的な感情もまた、存在している。私たちは、自分で選ぶことなく生まれながら、様々な偶然の巡り合わせによって人と出会い、それぞれの物語を紡いでゆく。
そんなことを考えながら、三十代という人生のミドルノートの時間を生きる主人公たちを書くことは、とても楽しかった。
★ブックレビュー

人生の“ミドルノート”にある女性たちをしなやかに肯定する物語 吉田伸子(書評家)
あぁ、そうか、時とともに香りが移り変わっていく香水は、人生と似ているのだ。本書を読み終えて、そのことに気付くと、タイトルである「ミドルノート」の意味が、ぐっと深くなる。
物語は、三芳菜々、板倉麻衣、江原愛美、岡崎彩子、という四人の女性、それぞれの視点で語られていく。菜々と麻衣、愛美は新卒で入社した食品会社の同期であり、同じ工場で研修を受けたことから絆ができ、麻衣が早々に退社した今でも繋がっている。彩子は菜々の隣の部署で働く派遣社員だ。
菜々の夫・拓也も麻衣、愛美とともに研修を受けた同期であり、同じく西孝義、坂東賢太郎を加えた六人は「イツメン(いつものメンバー)」として、入社後十年近くを経ても交流がある。
妊娠中の菜々は、身軽なうちにみんなと楽しいひと時を過ごしたいと、イツメン+彩子を拓也との新居に招く。楽しく、和やかな時間が過ぎ、幸せな気持ちでマンションのエントランスまでみんなを見送った菜々だったが、部屋に戻ると片付けを任せていた拓也から、もう家に人を呼ぶのはやめよう、と言われてしまう。拓也からのキツい言葉に、菜々は傷つく。
麻衣は菜々の家からの帰り、愛美と坂東と入ったショットバーで、ふと過去を振り返る。会社を辞め、アロマデザイナーの道を歩んだことに後悔はない。とはいえ、店にいた若いグループに、かつての自分たちの面影を見て、不意に切なさをおぼえる。
愛美は、二十代で課長に昇進、同期イツメンのなかではトップの出世を果たしているものの、所詮は「お飾り」でしかないことを痛感している。
彩子は菜々たちが勤務する食品会社で、ようやく職場での人間関係に恵まれた、と感じている。それまでの職場では、同性からは意味なく疎まれたり、異性の「変な人」から思いを寄せられたりしていたのだ。その都度、職場を変えていた彩子にとって、今の職場は「ようやく深呼吸できる」場だった。
物語は、「Before……」と「After……」「With……」の三章構成になっている。その間、三年ほどの時間が経っている、という設定なのだが、この、三年という時間が物語の中で効いてくる。
全文はこちらへ →https://j-nbooks.jp/novel/columnDetail.php?cKey=205
★著者プロフィール
 写真/中川正子
写真/中川正子あさひな・あすか
1976年東京都生まれ。会社員を経て、2000年にノンフィクション『光さす故郷へ』(マガジンハウス)を刊行。06年、群像新人文学賞受賞作『憂鬱なハスビーン』(講談社)で作家デビュー。以降、働く女性や子ども同士の関係を題材に、多数の作品を執筆。主な著書に『闘う女』(小社)、『憧れの女の子』『自画像』『人生のピース』『ななみの海』(双葉社)、『あの子が欲しい』(講談社)、『さよなら獣』 (中央公論新社)、『人間タワー』(文藝春秋)、『君たちは今が世界(すべて)』(KADOKAWA)、『翼の翼』(光文社)などがある。
arrow_upwardページトップへ


